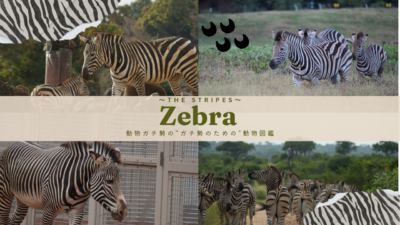サファリで大人気の“スターたち”いわゆる“BIG 5”(ライオン、ゾウ、スイギュウ、サイ、ヒョウ)にたいして、“ブサイク”という意味の名前をつけられた“Ugly 5”という不名誉な動物たちがいることをご存じでしょうか…
個人の感想ですが全く醜くない、魅力にあふれる動物たちです。
ぜひ彼らの魅力に触れてみましょう!
Ugly 5とは
“Ugly 5”には、以下の5種類が当てはまります。
- ハイエナ
- イボイノシシ
- ハゲワシ
- アフリカハゲコウ
- ヌー
あまり動物に詳しくない方にとっては馴染みのない動物たちかもしれませんね…
醜いといわれてしまっていますが、僕は彼らが大好きですし、アフリカの大自然や生態系において欠かせない大事な役割を果たしています!!
それでは彼らについて、詳しく見ていきましょう!!
“唯一ディ〇ニーにキレていい動物” ハイエナ

死肉をむさぼり、獲物を奪い取る…そんなイメージがあるんじゃないでしょうか?
“ハイエナ”と呼ばれる生き物はいろいろと横取りするタイプの人間を除けば4種います。
- ブチハイエナ
- シマハイエナ
- カッショクハイエナ
- アードウォルフ
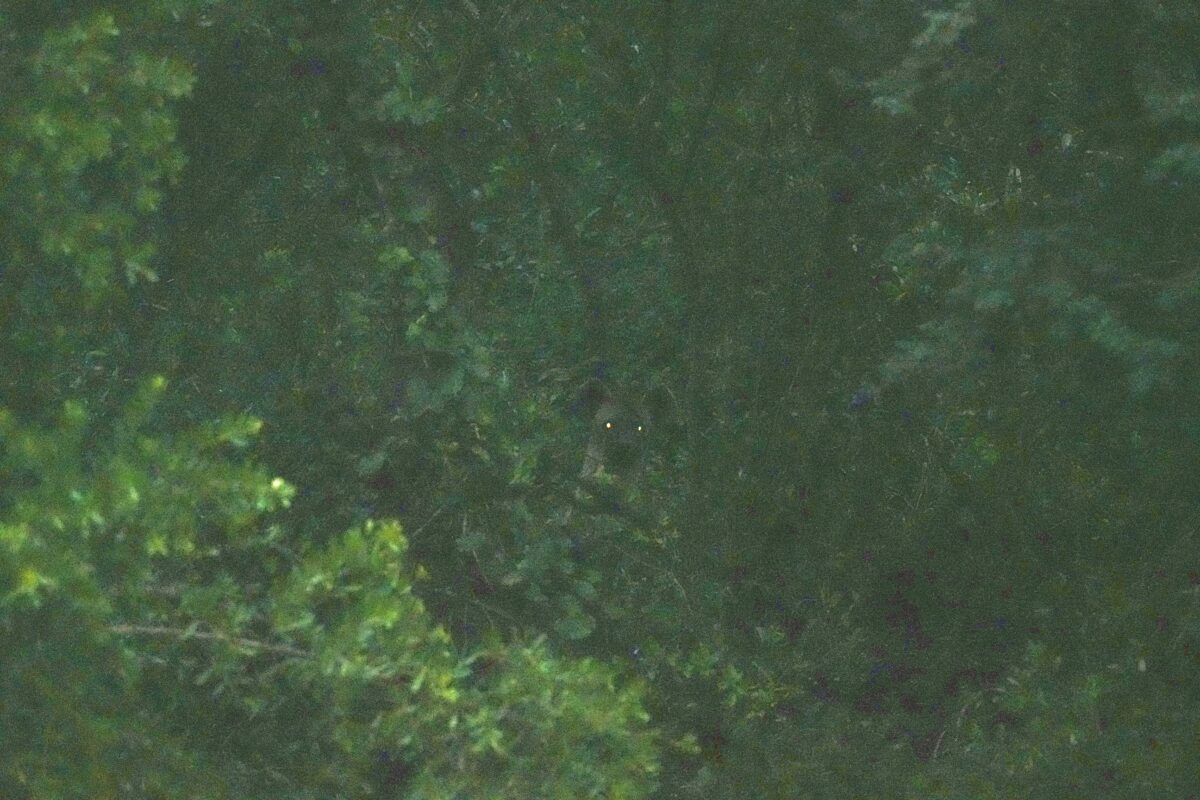
ブチハイエナ(学名:Crocuta crocuta)はそんなイメージとは全く異なる生き物です。メスをリーダーとするクラン(Clan)という群れを形成して狩りをしますが、その狩りの成功率は60-70%!! サバンナに生きるほかの捕食者のほとんどを上回ります。自分たち自身で狩りをすることも多く、優れた名ハンターなんです!!
 Ryusei
Ryusei何ならライオンの方が横取りしてたり…


そして彼らの最もすごい所はその食性です!
噛む力がとても強いというのは有名な話ですが、ブチハイエナの嚙む力(咬合力)は約5000Nといわれており、大体成人男性7人(約500kg)に圧し潰されるのと同じ衝撃で獲物を嚙み砕きます。これのおかげで頭蓋骨や大腿骨などの大きく硬い骨まで粉砕し食べます。彼らの胃酸はとても強力で、そのpHは1.0前後(ブチハイエナ)といわれています。人間の胃酸は一般的にpH2ほどといわれているため、かなり強いと言えます。強力な胃酸を持つため、我々では消化できないような骨や蹄まで消化できます。
さらにすごいのが、多くの細菌に対し感染することなく消化できます。強力な胃酸や消化管内に対病原菌構造を持っているため全く問題ありません。
彼らがもし、病気に感染した動物の死体を食べてくれなかったら…いつまでも遺体は残り続け、より多くの動物が死滅し、人間も影響を受けるでしょう…
某映画で悪役にされ酷いイメージが定着し、醜い生き物といわれているハイエナ…不憫すぎますね…



ちなみに、今回紹介したのは狩りも得意なブチハイエナ
死肉食に特化したシマハイエナやカッショクハイエナはどんだけ強いのか…ご想像にお任せします
“ハクナマタタなんて性格じゃない” イボイノシシ


普通のイノシシや豚とは一線を画す生き物がこのイボイノシシです。かつては一種類のみと思われていた本種ですが、現在はイボイノシシ属として二種「ケープイボイノシシ(学名:Phacochoerus africanus)」「サバクイボイノシシ(もしくは単にイボイノシシ・学名:Phacochoerus aethiopicus)」に分類されています。今回使っている写真は全て南アフリカで撮影したものなので、ケープイボイノシシになります。



ケープイボイノシシは上顎の前歯がありますが、サバクイボイノシシは無いのが特徴ですね!!(パッと見でわかるわけない)
某映画内では「心配ないさ!」と楽観的でちょっと間抜けに描かれている本種ですが、実際はそんなイメージとは異なります。


イボイノシシは二ホンイノシシなどと比較すると臆病であり、警戒心が強く逃走する傾向が強いです。
実際観察していてもすぐに逃げてしまって中々観察しにくい生き物でした。
しかし、逃げられないときや興奮しているときはとんでもなく危険な生き物です。
彼らは瞬時に最高時速50㎞まで加速し、数百メートルを最高速度で駆け抜けていきます。
この速度で逃げてくれればいいのですが、彼らの攻撃方法は突進からの牙による斬り上げ攻撃…
最大30cmにもなる鋭い牙で切り裂きます。
しかも彼らは“サウンダー(Sounder)”といわれる小規模の群れを形成していることがほとんどです。
時速50kmで鋭い牙が複数飛んでくるって…醜いとか言ってられないですね


「あ!プ〇バァだ!」とかいって不用意に近づいたり、ナメてかかるとすぐに突進されて下半身が”破”クナマタタしますのでお気を付けください
“愛すべきハゲ” ハゲワシ


皆さんの言いたいことはわかります。
ハゲワシは醜いよ
確かに死骸に群がり、肉を引きちぎる姿は醜いといえるかもしれませんね…もはや名前にハゲってついてますし…
しかし!
見た目では判断できないすごすぎる能力があります。
それが、どんなものでも食べる事が出来る消化能力です。


彼らの胃酸は驚異のpH0.5から1を誇ります。ハイエナさえしのぐ強酸…骨や蹄などはもちろんどんなものも食べられます!この酸のおかげでほとんどの菌は無力化できます。
更に彼らの腸内細菌には、生物兵器として用いられたことのある炭疽菌やボツリヌス症を引き起こすボツリヌス菌など致死性の細菌を抑制する微生物嚢(びせいぶつのう:微生物の集合体のこと)が存在します。これらの微生物で強力な菌を抑えつつ、腸管内を通過させる時間を短くすることで大腸内からの感染を防ぎます。
彼らが強力な菌を保持する遺体を処理してくれるおかげで多くの病原菌が無力化されていると言えます。
しかし、体内でいかに病原菌を処理できても体外に付着してしまっていては巣に持ち帰ったり移動した際に菌をまき散らしてしまいます...
そこでハゲワシはとんでもない行動を行うようになりました。なんと自分のフンを自分の足にかけるのです!!
「ウロヒドローシス」と呼ばれるこの行動にはジョージア大学の研究により病原菌の抑制作用が確認されています。一見汚いように見える行動ですが、病原菌を広めないようにするための大切な行動なのです。人間で例えるとアルコール消毒に近いかも…?
この“きれいな頭”も死体に頭を突っ込んで食べるときに汚れが付着しにくいようにハゲているのです。
そんな腐肉食に特化した彼らも唯一消化できないものがあります。それが重金属類や農薬など、人間が作成したものです。現地ではまだ鉛製の弾丸を狩猟に用いていることも多く、放置された死体を食べに来たハゲワシがその鉛玉を誤飲し鉛中毒で死亡するという事故も発生しています。
動物から人間に感染する人獣共通感染症を防ぐためにもこのような事故を減らし、ハゲワシたちをしっかり守っていくことが必要です!まずは彼らの事を知ることからですね!!



ハゲとか言ってる場合じゃねぇ!!!
“普通に名前が悪口” アフリカハゲコウ


はい、もう一回ハゲが出てきましたw
そして恐らく、あまり動物に詳しくない方々はこう思っていることでしょう…
…誰!?
それもそのはず今回のUgly 5の中でダントツの知名度の低さを誇るのがこのアフリカハゲコウ(学名:Leptoptilos crumenifer)なのです。crumenifer(膨らんだ袋を持つ)のとおり、首元にペリカンのような大きな袋を持つのが特徴になります。
…まあそれよりも気になるのは一部男性陣が不安になるような頭でしょう。
なぜこんなハゲ散らかした頭をしているかというと、彼らの食性が関係しています。
彼らの食性はハゲワシに非常に良く似ていて、主に腐肉食、時々小型の哺乳類も狩って捕食します。
しかし、胃酸のpH濃度や腸内の微生物嚢などに関する研究は進んでおらず、明確なデータはありませんでした。
組織に含まれる細菌類は胃の中で不活化されているとの報告もあり(Houston (1988)、Mundy (1992))、胃酸はpH1未満程度と推定されています。
ここまでの情報ではほぼハゲワシと同一ですが、いくつか異なる点があります。それは体格と適応能力です。
まずこのハゲた巨鳥は翼を広げると約3m、直立状態で1.5mにもなります。ハゲワシが翼開長2メートル前後(種により異なる)、体長1.3m以下の種がほとんどになりますので、いかに大型な種なのかがわかっていただけるかと思います。
そして適応能力...彼らは近年、アフリカ各地の都市部に現れ、ゴミをあさる事例が確認されています。
そしてその後死に至るような感染を引き起こした例は確認されていません。日光浴や水浴びなどによって病原体を排除していると考えられています。彼らの嘴は硬質ケラチンで構成されており、腐った肉に突っ込んでも感染を引き起こさないようになっています。ハゲワシにも見られた糞を自分の足にかけ殺菌する行為(ウロヒドローシス)も確認されているため、様々な方法によって病原体を排除適応していると考えられています。
ハゲワシと同様に彼らも未知の病原体を処理する一役を担っているのです。しかしまだ調査研究も進んでおらず、繁殖・野生復帰も難しい状況です。
それがいまだ謎多き怪鳥、アフリカハゲコウなのです。





2024年6月、秋吉台サファリランド国内初めての繁殖に成功しました!!2025年にも繁殖成功しており、今後の域外保全に期待されます!!
“プロポーション×、でもマニアは大好き” ヌー


Ugly 5最大の動物、それがヌーです。
現生種においてはオグロヌー(学名:Connochaetes taurinus)とオジロヌー(学名:Connochaetes gnou)の2種が知られており、さらにオグロヌーはシロヒゲオグロヌーやクロヒゲオグロヌー、シロオビオグロヌーなど5亜種に分けられます(オジロヌーは単型種と呼ばれ、亜種は認められていません)。
一部の伝説では、神が世界を創造し動物を形作った際に、あまりもの(バッファローの角、イナゴの顔、ウシの体、ライオンの尾、ヤギの足)をつなぎ合わせて作ってのがヌーだといわれています…
英名もWildebeest、オランダ語の野獣が元になっており、もはやただの獣としか呼ばれてませんw
他の“Ugly 5”は理由があって罵倒されていますが、本種に関してはただプロポーションの問題で適当にあしらわれています。


そんな彼らも大切な役割があります。
それは生態系における被食者であり、多くの生き物の栄養となることです。彼らは雨期になると一斉に出産し大量の赤ちゃんが生まれます。さらにケニアなど東アフリカに生息する個体群は乾季の大移動で百万頭以上にもなる群れを形成します。大移動の経路は過酷を極め、経路に待ち伏せするライオンに襲われたり、川を渡る際にワニに襲われたり溺死する個体も続出します。米国科学アカデミー紀要に掲載された研究発表によれば、ケニア・タンザニア間に流れるマラ川では一年で平均6250頭ものヌーが死亡することがわかりました。体重換算で約1100t、シロナガスクジラ10頭分の遺体が川に流れるのです。
これだけの数が亡くなるとワニやライオンが食べきれないレベルになります。食べきれなかった遺体や残った骨は川に残ります。その結果、多くの栄養素が川に溶け込んだり、魚や小動物の餌になったり、長期的に川に栄養素を補給する役目も果たしているのです。
ほかにもシマウマやガゼルと群れを組んで大群をなして肉食動物への警戒能力を高めたり、いろんな役割があります。
やっぱり見た目が十割じゃないってことですね!!
今回紹介した5種の動物たち、みんな見た目が悪い、気持ち悪いという理由でUgly 5に入れられています。
それが原因で駆除や保全、研究が進まないということも起きています。見た目だけではわからない、様々な魅力もあるし、生態系にはどんな種類も欠かせないのです!!
今回の記事を読んで、少しでも彼らの魅力が伝われば幸いです。
- Wroe et al. (2005)、Christiansen & Wroe (2007)
- Estes, R. (1992) The Behavior Guide to African Mammals
- Roggenbuck et al. (2014:腸内細菌研究)
- DeVault, T.L., Rhodes, O.E., & Shivik, J.A. (2004) “Scavenging ecology and disease risk”