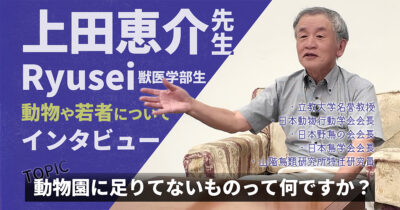はじめに
「みんなのアニマルアカデミア」第2回目です。
今回はRyusei編集長……ではなく、かずぺでぃあがお届けします。
【“みんなの”アニマルアカデミア】ですからね。1人だけでなくみんなで情報を発信していきます!
1人でも多くの方から情報を発信することで、多角的な視点から物事を見ることができます。それにより、偏りなく考え、学ぶことができるんですね!
【みんなのアニマルアカデミア】は多くの方々から知見を得られるシリーズを目指します。
今後ともよろしくお願いいたします。
今回のテーマ
そんな【みんなのアニマルアカデミア】第2回のテーマは…
環境エンリッチメントについてです。
前回は「そもそも『動物福祉』って何?」というテーマで動物福祉についてRyusei編集長と一緒に学びましたね。
動物福祉とは「動物の心と体の状態」。動物の主観的状態を判断するために「5つの自由」という基準を用いることや、どうして動物福祉に配慮する必要があるのかについて紹介しました!

その動物福祉を改善するための取り組みの1つが「環境エンリッチメント」です。
これに関しても、動物福祉と同様に勘違いをしている方も見受けられます。一緒に環境エンリッチメントについて学んで、正しい知識を身につけましょう!
 Ryusei
Ryusei僕も間違った解釈をずっとしていました…



自分の解釈と合致しているか確認してみましょう!
環境エンリッチメントとは
まずは、環境エンリッチメントの概要について解説します。
環境エンリッチメントって、なに?
環境エンリッチメントとは特定の“モノ”を指し示す言葉ではありません。
その定義は様々ですが、詳細に書き記すと以下の様になります。
ざっくりと言ってしまえば、「動物の生活をより良くするための施策すべてを指す言葉」です。
“モノ”を与えて動物福祉を向上するのは環境エンリッチメントの1手段なので「エンリッチメントを与える」という表現は間違っていることになります。



この後紹介する“フィーダー”と混同している方が多い印象ですね。



目に見えないエンリッチメントもあるんやで~
環境エンリッチメントが始まったきっかけ
では、どうして環境エンリッチメントを行う必要があるのでしょうか?
それを理解するためにも、まずは動物飼育の歴史を紐解いてみましょう
人間都合から始まった動物飼育


数十年前の動物園は野生動物への知識が乏しく、どれくらいの力があって、何を食べているのかわからない状況でした。さらに、多くの人が出入りするので、感染症の心配も……。そんな中で野生動物をつれてきたので、環境や生活の質よりも安全性や衛生面が重要視されました。そのため、飼育施設は頑丈な鉄格子や扉に、清掃・殺菌処理が容易なコンクリート製のものと、当時は人間の都合による飼育環境が主流だったのです。
シンプルな檻には先述の通り、安全性や衛生面でのメリットがあります。
「コンクリート製の檻=悪い展示」ではありません。
環境エンリッチメントの礎「行動エンリッチメント」
そんな中で、飼育下の動物の環境やその生活の質を高めることが有益だという考えは「動物園生物学の父」と知られている「ハイニ・ヘディガー(Heini Hediger)」によって1950年代より提唱されました。しかし、当時はあまり注目されませんでした。
この考えが注目されるようになったのが「ハル・マーコウィッツ(Hal Markowitz)」による「行動工学」。
のちに「行動エンリッチメント」と呼ばれる施策でした。
この行動エンリッチメントは「オペラント条件付け」に基づいたものです。飼育動物が望ましい行動をしたときに報酬としてエサを与えることで、それらの行動をする機会が増加します。マーコウィッツはそれによって動物の望ましい行動を刺激したり、活動性を高めたり、健康管理が楽になったりするだろうと考えました。
しかし、これは強い批判を受けました。
この「行動エンリッチメント」によって引き出される行動は「自然的」ではなく「人工的」だったからです。
「エサを獲得するために、装置のレバーを押す」。確かに行動の発現には成功しています。
しかし、これは野生下の行動とは乖離した行動であり、行動と環境の関係性を動物自身が理解していないとされ、動物の行動を“人工的”にではなく、“自然的”に増やす代替手段が求められました。
この代替手段こそが環境エンリッチメントなのです。
人間ファーストから動物ファーストへ


野生動物の研究も進み、動物や感染症等への正しい知識が深まりました。これにより、動物たちの寿命は伸び、繁殖例も増えました。しかし、動物園で誕生した動物たちにおける「繁殖障害」や「発育障害」、「社会的問題」「異常行動」といった問題は解決されませんでした。
その原因として「飼育管理しやすいように、単純な獣舎で飼育すること」や「健康管理しやすいように、決まった時間に決まった量のエサを与えること」といった、単純な飼育管理方法にあると考えられました。
というのも、これらは動物たちにとっては退屈で、変化のないものだったからです。
そこで注目されたのが「環境エンリッチメント」でした。動物の行動機会を自然的に増やすことができれば、退屈な時間が減り、変化に富んだ飼育ができます。これによって、数々の問題は徐々に解消されてきました。
動物たちに“より豊かで幸せな日々”を過ごしてもらうためにも、様々な工夫や試みが今日も各園で行われています。
環境エンリッチメントの目的
以上のように、環境エンリッチメントは動物たちを幸せにするために実践されるようになりました。
しかし、環境エンリッチメントの“目的”はそれだけで言い表すことはできません。
主に以下の3つが環境エンリッチメントの目的と言えます。
- 野生と同様の行動の発現
- 望ましい行動の促進と望ましくない行動の抑制
- 活動性と行動の多様性の増加
1.野生と同様の行動をしてもらう




環境エンリッチメントは“野生と同様の行動”=“自然な行動”を発現させるために行われます。
例えば、綺麗な場所に置かれたエサを「その場で食べるサル」と「木に登ってからエサを食べるサル」。
どちらが自然に近いでしょうか?
もちろん、後者ですよね。
自然に近い行動を発現させることで、その活動性が高まります。
2.望ましくない行動を抑制する




動物園をはじめとした飼育下個体は、常同行動や自傷行為など、野生下では絶対にしない「異常行動」をします。
もちろん、それは望ましいことではありません。
そこで、環境エンリッチメントによって「自然に近い行動を発現」=「望ましい行動を促進」し、それを行う時間を増やすことで、異常行動を抑制することができます。
3.活動性と行動の多様性を増やす




「寝ているライオン」と「起きているライオン」。多くの来園者がどちらを見たいのかは一目瞭然ですよね。
寝るという行為も立派な「行動」ですが、寝ている“だけ”では行動のレパートリーが不足してしまいます。
そうなると、動物と来園者、双方にとって退屈な時間になってしまいます。
それを防ぐためにも環境エンリッチメントは活用されています。



ヒトを含めた動物を満足させることができるのだ!
環境エンリッチメントの方法
さて、環境エンリッチメントの概要と目的がわかりましたね。
続いては、その方法と具体例について見ていきましょう
5つのカテゴリー
環境エンリッチメントは様々な方法がありますが、その意味によって5つのカテゴリーに分けることができます。
- 採食エンリッチメント
- 空間エンリッチメント
- 感覚エンリッチメント
- 社会エンリッチメント
- 認知エンリッチメント
このようにカテゴリー分けをすることで、環境エンリッチメントを実践しやすくするだけでなく、期待される効果の目安にもなります。
では、各カテゴリーの詳細を見ていきましょう。
1.採食エンリッチメント
採食エンリッチメントはその名の通り、動物たちのエサに関する工夫のことです。


野生動物は一日の大半をエサを探したり、加工したり、食べたりする時間に費やします。
その一方で、動物園では加工済みのエサが毎日出されるので、動物たちは苦労なくエサを食べることができます。
その結果、エサを探す行動(索餌行動)も、食べる行動(採食行動)の機会も時間も少なくなってしまいました。
その問題を解決するために採食時間を延ばすことを目的とした取り組みこそが「採食エンリッチメント」です。
代表例として、「フィーダー(給餌器)」という道具を使った「動物たちが遊びながらエサを食べられる」給餌方法が挙げられます。


しかし、採食エンリッチメントはフィーダーだけではありません。「エサを隠して探してもらう」「一度に与えるエサを減らして索餌行動を増やす」「普段は与えないエサを与える」といったことも立派な採食エンリッチメントです。
このように豊富な手段があるのに加えて、動物のエサに対する意欲は大きいことから、最も広く利用されているエンリッチメントと言えるでしょう。
2.空間エンリッチメント
空間エンリッチメントは、動物の行動特性に合った空間をつくる工夫のことです。


安全・安心かつ衛生面の管理もしやすいコンクリート性の飼育環境は確かに合理的です。しかし、それだけで動物が持つ本来の行動を引き出せず、異常行動の発現やストレスをため込む原因になってしまいます。
樹上性の動物には登り木を、半水生の動物には泳ぎ回ることができるプールをそれぞれ用意し、各動物種に適した行動機会を与えることができる空間をつくる工夫が「空間エンリッチメント」です。
行動発現に留まらず、人目によるストレスや日照による過度な体温上昇を避けられる隠れ家や日除けを追加するといった、快適な空間を提供するのもその一環と言えます。
3.社会エンリッチメント
社会エンリッチメントは、動物種の社会性に適した飼育環境を構築する工夫のことです。


群れをつくる・ペアで暮らす・単独で生活するといったように、動物種によってその社会性は異なります。群れをつくる動物なら「多頭飼育して群れをつくる」というように、その動物種に適した社会環境にする必要があります。
また、他種との交流をできるようにする取り組みも該当します。ここでいう「他種」とは「ヒト」も含まれます。
同種・他種に関わらず、ヒトを含めた社会性を構築するのが「社会エンリッチメント」の本質と言えるでしょう。
4.感覚エンリッチメント
感覚エンリッチメントは、動物の五感を刺激して環境や行動に変化をもたらす取り組みのことです。


【視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚】これら5つの感覚「五感」も動物種によって異なります。それらを刺激することが、動物の行動の多様化に繋がるんです。例えば、別個体の臭いが残った放飼場に出せば、臭いを嗅ぎながら探索したり、マーキングをして臭いを上書きしたり、フレーメン反応をしたりと様々な行動へ派生します。
1つの感覚を例に挙げるだけでも多くの行動を発現できるため、「感覚エンリッチメント」は採食エンリッチメントと同様に多くの動物園で取り組まれています。
5.認知エンリッチメント
認知エンリッチメントは、好奇心や探求心といった知性を刺激し、動物自身が考えて行動できるようにする工夫のことを言います。


複雑な動きをするおもちゃや遊具は、知能の高い動物にとって「心を豊かにする」ものだと言われています。
「考えても何もできない」環境よりも「考えながら何かができる」環境の方が断然良いですからね。
それを実現する取り組みこそが「認知エンリッチメント」です。
近年は認知実験も環境エンリッチメントの1つとして取り組まれていますね。
各動物園の実践例
現在は、この5つのカテゴリーに基づいて、多種多様な環境エンリッチメントへの取り組みが行われています。
なお「1つの取り組みに対して、1つのカテゴリーが当てはまる」なんてことはありません。
「1つの取り組みに対して、複数のカテゴリーが当てはまる」ことがほとんどです。
それではここで、注目したい取り組みをいくつかご紹介いたしましょう。
千葉市動物公園 ―― ライオンのミートキャッチャー




- 採食エンリッチメント
-
獲物を狩る際の動きを再現した行動を引き出しながら、ライオンにエサを与えることができる。
- 感覚エンリッチメント
-
肉を目で追う、使用した藁の残り香を嗅ぐといった感覚を刺激する
多摩動物公園 ―― オランウータンのスカイウォーク




- 空間エンリッチメント
-
樹上性のオランウータンが木々を渡る様子を再現する。
- 感覚エンリッチメント
-
高所からものを見せたり、風や日光など高所ならではの環境が五感を刺激する。
また、人工物メインの展示場と植物メインの展示場を往来させ、異なる刺激を与えることができる。 - 社会エンリッチメント
-
親が子へ木登りの仕方を教える機会をつくる。
よこはま動物園ズーラシア ―― チーターラン




- 空間エンリッチメント
-
チーターが駆け回れるほどの広い放飼場を設ける。
- 感覚エンリッチメント
-
狩猟時の動きを再現し、運動不足の解消に繋げる。
より良い環境エンリッチメントを実現するために
環境エンリッチメントの仕組みや課題を理解する
コントラフリーローディング
「コントラフリーローディング」という言葉をご存知でしょうか?
コントラフリーローディングとは「楽に手に入れたものより、苦労して手に入れたものの方を好む」という心理的傾向の事を言います。
皆さん、こんな経験はありませんか?
- レトルトのカレーより、自分でつくったカレーの方が美味しい
- 完成された家具よりも、自分で組み立てた家具の方が好き
- ゲームで苦労して育てたキャラクターに愛着が湧く



これこそがコントラフリーローディングの効果です。



簡単に言い換えれば「思い入れ補正」ということですね!
実は、この効果はヒトだけでなく全ての動物で見ることができます。
これに関してある実験が行われました。マウスに「普通に置いたエサ」と「レバーを押すと出るエサ」を同時に与えた所、「レバーを押すと出るエサ」を選択したのです。
そしてこれは、サルや未就学児にも同様の結果が得られました。
このことから、脳は「簡単に手に入るもの」よりも「苦労して手に入れたもの」を好むことがおわかりいただけたと思います。
環境エンリッチメントが成立するのは、この「コントラフリーローディング」が働いているからと考えられています。
自力でエサを見つけたり、五感で何かを得られたりすることは、動物たちにとってこれほどまでにない「報酬」になります。そのようなことができる飼育環境を実現することこそが環境エンリッチメントの神髄と言えるでしょう。
環境エンリッチメントの安全性


これまで、環境エンリッチメントの利点について触れてきましたが、課題点も存在します。
その例の1つが「環境エンリッチメントの安全性」です。
どんなに素晴らしい効果が得られる取り組みでも、危害を与える可能性があるのであれば避けるべきです。
例えば、生餌を使った採食エンリッチメントの場合。生餌は動物の狩猟本能を刺激し、野生本来の採食行動を引き出せます。しかし、衝突事故が起こる可能性があるため、全ての動物種で行うことは不可能です。
ハシビロコウの場合、生餌はコイなどの魚になります。生餌の行動範囲は水中に限られるので問題はありませんね。
では、フクロウの場合はどうでしょうか?彼らの主な獲物はネズミになります。ネズミは展示場の全体を移動できてしまうため、逃げ回るネズミを追ってフクロウが壁に衝突してしまう危険性があります。
ということは、フクロウにネズミを生餌として与えることは不適切と言えますね。
生餌以外にも「フィーダーの穴に鼻や手がハマってしまう」「おもちゃを誤飲してしまう」といった事故だけでなく「エンリッチメント装置を独占しようとする」といった「闘争の原因」になってしまうこともあります。
このように、環境エンリッチメントを実施する際は「効果」だけでなく「安全性」も考えなければならないのです。
物珍しさと慣れ




環境エンリッチメントにおいて避けては通れない課題はもう一つあります。
それは「動物が慣れてしまうこと」です。
皆さんも、新しく買った便利グッズは物珍しさでとにかく使うと思いますが、慣れてくると便利グッズを使わなくなる時、ありませんか?
それと同じ現象が動物たちにも起こるんです。
フィーダーを使えば、採食時間が伸びて動物の暇な時間を減らすことができます。
しかし、そのフィーダーの仕組みに慣れてしまえば、伸びていた採食時間もだんだん少なくなってしまいます。
また、新しい植物を植えれば最初は興味深々ですが、だんだん慣れて最終的には手を出さなくなります。
以上の様に「慣れ」によって環境エンリッチメントの効果は永続するわけではありません。
「時間を空けて与える」「随時追加する」といったような対策をとる必要性があるのです。
ですが、これは悪いことだけではありません。これを逆手にとれば今後の動物飼育に役立てることもできます。
例えば、千葉市動物公園において、ゴリラの展示場に植物を植える取り組みが行われました。
その際、それぞれの植物に対してどのくらい興味を示すのか、その興味がどのくらい持続するのかを観察し、その結果を踏まえることで、今後ゴリラの新しい展示をつくる際にどの植物を植えるべきなのかを調査したのです。
- ゴリラが食べた植物
→採食エンリッチメントとして有効 - ゴリラが食べなかったが、何かしらの反応はした植物
→感覚エンリッチメントとして有効 - ゴリラが手をださなかった植物
→展示場の景観づくりとして有効
小さな積み重ね ―― SPIDERモデル
環境エンリッチメントは様々な動物園・水族館にて、多くの飼育員たちが小さな試行錯誤を繰り返し、それを継続してきた“積み重ね”によって発展してきました。これを体現したのが「SPIDERモデル」です。
「SPIDERモデル」とはディズニーアニマルキングダムが開発した方法で「PDCAサイクル」に似ており、それをより発展させ、動物園に特化したものと言えますね。
「SPIDERモデル」は以下の流れを繰り返し行うことで、飼育環境や環境エンリッチメントを改善していきます。
現在の行動を観察し、どんな行動を引き出したいかを論理的に考える
例)サルたちのQOLを改善したい
設定した目標に基づいた計画を立てる
例)給餌内容を野生本来の食性に近づければQOLは上がるのではないか?
計画を実行する
例)エサを生野菜メインにする、給餌時間をランダムにするetc…
実行した結果を記録する
例)エサを変更する前の姿と、変更した後の姿をそれぞれ記録する
実行した計画の評価をする
例)給餌内容の変更前後の記録を比較した結果、毛量・毛艶が改善された!
評価をもとに、改善策や更なる施策を見出す
例)フィーダーを追加し、給餌方法に変化を与えてみよう!
これまで紹介してきた事例も、このSPIDERモデルに基づいた改善が行われています。
そして、このSPIDERモデルを繰り返し、動物たちの飼育環境を大幅に改善した代表例といえば……。
ズバリ、飯田市立動物園の「QOLあげあげモンキーアパート」でしょう。
こちらの詳細は別の記事にて詳しく紹介しております。そちらも是非ご覧ください。





今回の内容を踏まえて読めば新しい発見があるかも!
環境エンリッチメントを評価する
SPIDERモデルにもあった通り、環境エンリッチメントをより良いものにするためには、それぞれの取り組みを「評価」しなければなりません。しかし、動物たちは「ここが良かった」とか喋って教えてはくれません。そのため、何らかの尺度をもって“客観的に”評価する必要があります。
では、その「客観的な評価」にはいったいどのような方法があるのでしょうか?
動物園での行動と野生での行動を比較する


第一に挙げられる例として、「飼育個体と野生個体の行動を比較する」ことが挙げられます。
環境エンリッチメントは「野生と同様の行動の発現」が目的の1つですから、飼育個体が野生個体と同様の行動をとったことを確認できたのであれば、その取り組みは大成功と言えるでしょう!
しかし、言うだけなら簡単ですが、野生個体が生息する地域へ移動し、観察をするためには費用や人員といったコストがかかります。また、どんなにコストをかけても、目当ての動物を100%観察できる保証はありません。
その一方で、現地の環境を見るだけでも、その動物を展示する空間をデザインするヒントを得られるといった副次的な利点があります。また、この方法は飼育個体への直接的な負担がありません。
そのため、「コストがかかる」という点に目をつむれば、最適な評価方法と言えますね。
動物のストレスホルモンを測定する


しかし「コストがかかる」という点は避けては通れない課題です。
園館によってはやりたくてもできない場合もあります。
そこで、糞や尿から「ストレスホルモン代謝物」を計測することで、環境エンリッチメントの効果を評価する方法があります。環境エンリッチメントに取り組む前後でストレスホルモンを計測し、それが有意に下がっていれば、「その取り組みは適切である」ということができますね。
動物の繁殖成功率を指標とする


動物たちにとってもらいたい「自然と同様の行動」の中には「動物の自然繁殖」も含まれます。
そのため、自然繁殖の成功は環境エンリッチメントの評価における立派な指標となります。
自然環境を再現した立派な飼育施設でも、自然繁殖ができなければそれは動物にとって適切な環境とは言えません。
それに対して、飼育施設が古かったとしても、環境エンリッチメントへの取り組みが万全であれば自然繁殖に繋がります。
動物園・水族館に留まらない「環境エンリッチメント」


今回は動物園での事例を中心に取り上げましたが、環境エンリッチメントは水族館でももちろん取り組まれています。
そして、動物園や水族館といった生体展示や動物保全の場以外でも重要なんです。
ペット ―― “家族”とより良い時間を過ごす




ペット達により良い日々を送ってもらいたいなら、環境エンリッチメントを率先して行いましょう。
例えば、イヌを散歩へ連れてったり、ドッグランで運動をさせることは感覚エンリッチメントの一環と言えます。
ねこじゃらしでネコと遊ぶのも立派な感覚エンリッチメントです。
また、幼体・成体・高齢個体と年齢に合わせてエサを変えることは採食エンリッチメントに繋がります。




ペットの飼育環境を構築する際も環境エンリッチメントの考え方が役立ちます。
「カイウサギ」は巣穴を掘ってくらす「アナウサギ」を品種改良した動物なので、広々とした飼育環境よりも巣箱やケージといった狭い環境の方が落ち着いて過ごすことができます。もちろん、運動も必要ですが常に広い場所で警戒するよりも、狭い場所で落ち着いてくれてた方が良いですよね。これも空間エンリッチメントの一種と言えるでしょう。
トカゲやカメといった爬虫類を飼育する際は体温調節のために、飼育ケージ内に「バスキングライト」をつけて疑似的な日光浴ができる環境を用意する必要があります。
また、種によっては登り棒や深い水場も必要になるので、飼育する種にはどんな環境が必要なのかを事前に調べる必要があります。
ペットは大切な“家族”です。その家族が一日でも長生きしてくれるように、環境エンリッチメントに基づいた飼育をしていきましょう!
家畜動物 ―― 生産物の質を高める




家畜動物の飼育においても環境エンリッチメントは役立っています。
例え短い命であったとしても、生きている間は動物福祉を高い水準で維持する必要があります。
それに、心身ともに健康に育った家畜動物は栄養価が高くなります。それによって肉付きがよくなり、乳量も増えるので、得られる生産物の量が増えるのです。
その方法としては、ウシならば定期的な放牧、自由に利用できる「フリーストール牛舎」の使用など。ブタならば泥浴びができる環境づくりや飼料の改善などが、それぞれ例として挙げられます。
実験動物 ―― 全ての動物のより良い暮らしのために




私たちの暮らしに欠かせない薬や化粧品、食料品をつくる際の試験のために飼育されている実験動物。彼らに対しても動物福祉への配慮は欠かせません。そのため、ここでも環境エンリッチメントが活躍します。
実験動物の代表であるマウスを例に挙げると、飼育環境に紙やウッドチップといった床材だけでなく、縮れた紙やティッシュを加えることで、巣作りができる環境をつくる取り組みが行われています。これにより、マウスの安心感が増幅し、闘争の防止や離乳の成功率向上に役立っています。
また、直接手で持つのではなく、シェルターを介して持つことでマウスのストレスを低減しているとの研究結果が出ています。
その一方で、環境エンリッチメントがどのように動物へ機能するのかを実験動物で試験する場合があります。
実験動物は私たち人間の暮らしを支えるだけでなく、動物園動物の暮らしも支えているのです。
まとめ


- 「環境エンリッチメント」とは「動物の生活をより良くするための施策すべてを指す言葉」である。
- 採食・空間・感覚・社会・認知の5つのカテゴリーに分けられる。
- 数々の施策は「SPIDERモデル」に基づいた小さな積み重ねの成果物である。
- 環境エンリッチメントは全ての動物飼育の場で活用されている。
以上、「環境エンリッチメント」についてでした!
ここまで読んでくださった皆様は……
動物の飼育環境や動物福祉を評価するのは「動物の飼育展示施設のつくりだけが全てではない」ということがおわかりいただけたと思います。
環境エンリッチメントに注目しながら動物を観察すれば、新しい動物園の楽しみ方ができることでしょう。
ぜひ、お試しあれ!



ところで編集長。
次回は誰がどんなことを話してくれるんですか?



それは次回のお楽しみですね!



・・・次回もお楽しみに!!