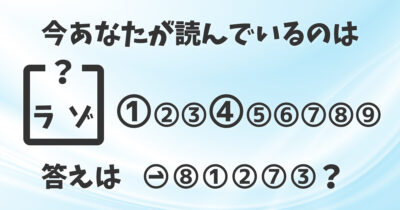動物園でいけばなをいける?!
華道家・古流松藤会家元の池田理英と申します。
動物が好きで日頃から時間があれば動物園に通っている私に、「動物園で花をいけられたら、やりますか?」という夢のようなご提案を頂いたのが2024年の春。お声がけくださったのは、公益財団法人 横浜市緑の協会(よこはま動物園ズーラシア・野毛山動物園・金沢動物園や横浜山手西洋館、横浜市内の公園などを運営)とのお仕事を何度もされている他流派の家元でした。
好きなものを公言し続けるって大事ですね。「やります!やりますとも!」と二つ返事で企画が始まる事となりました。
場所をご提供くださる事になったのは、横浜の桜木町からも程近い横浜市立野毛山動物園。

1951年の開園以来、多くの方に親しまれている入園無料の動物園です。
そして展示場所となったのは、その中にある「しろくまの家」。1959年から1999年まで実際にホッキョクグマを飼育展示していた施設です。その場所に、私とこの企画にお声がけくださった一葉式いけ花家元・粕谷尚弘先生とで花をいけるという企画です。
ホッキョクグマ好きとしてはしろくまの家を使わせていただけるなんて、、、感無量。準備段階から胸いっぱい。
自分にとっても大切な場所で、何をするか、どこに何をいけるか、少しのプレッシャーと共に考えるだけで胸躍る日々でした。

会期は2025年6月6日(金)~6月8日(日)。6月6日はいけばなの日です。古来より、「芸事は6歳の6月6日に始めると上達する」と言われている事などに由来しています。
動物園とのコラボならではの作品にするため動物園側も積極的にご協力くださり、さまざまな「動物のおとしもの」を作品に組み込む事ができました。
いけばな展示atしろくまの家
ホッキョクグマの飼育施設であった建物の各部屋にいけばな作品を展示。
- 廊下 粕谷尚弘先生作品

よく見るとヘビの抜け殻が作品に。

- オスの寝室 粕谷尚弘先生作品
寒い地域に生息するホッキョクグマが、自由になって南の島へ旅するイメージ。手前のエサ入れに置いてある竹筒はツキノワグマのサンペイがおもちゃとして使用したものです。

- メスの寝室 池田理英作品
動物達も夢を見るのかな、という事から構想を広げた作品。シロクジャクとオシドリの羽根をちりばめました。鳥好きの方はオシドリの銀杏羽に反応。


- 記録室 池田理英作品
隣の産室に藁が敷き詰めてあるところから繋がるような材料と、浮かび上がる魂のイメージ。

- 産室 池田理英作品
「しろくまの家」に生きた全てのホッキョクグマ、そして全ての動物に捧げる作品。ここに暮らしたホッキョクグマのシロキチ(♂)ユキ(♀)のペア、カンタ(♂)ユキコ(♀)のペアとの間に、育つ事はなかったものの出産があった場所でもあります。
ここに確かに生きたホッキョクグマ親子に思いを馳せながらいけました。


いけばなライブパフォーマンスatしろくまの家
展示初日でありいけばなの日でもある6月6日には、外の運動場でライブパフォーマンスも行いました。作品をいけていく過程をご覧いただくというものです。
ホッキョクグマを意識して衣装は白で。粕谷先生は意識どころかホッキョクグマコスプレの域。登場の瞬間ギャラリーはざわついておりました。

撮影:KEIKO


パフォーマンスの作品にも、動物園側からご提供いただいた「キリンが葉を食べた後の枝」「レッサーパンダが食べ残した竹」「クジャクの羽根」などを使わせていただきました。

そしてホッキョクグマオブジェにいけた作品には、、、、よこはま動物園ズーラシアさんからご提供いただいた、展示場でホッキョクグマに折られた植栽の枝と遊んだ後の遊具が!

ズーラシアのホッキョクグマ・イッちゃんが豪快に植栽を破壊する姿はホッキョクグマ好きの方は目にしたことがあるかもしれません。その光景を見て「あの枝、作品に使いたいな…」と常々思っていた私。その思いを叶えてくださった、横浜市緑の協会、野毛山動物園、ズーラシアの各関係者の皆様には感謝しかありません。
折れた枝や廃材でも、動物好きにとってはお宝中のお宝ですよね。

いけばな体験ワークショップatペンギン舎前屋内休憩所
来園者が実際に花をいける事ができるワークショップを、春にリニューアルしたばかりのペンギン舎前休憩所で行いました。
粕谷先生のワークショップは「水中花をいけよう」。水の中にお花をいけるという水遊び感覚のいけばなで、写真は粕谷先生がいけた特別バージョンです。ホッキョクグマがお花を抱えています。
私が担当したワークショップは「鳥の羽をいけよう」と題し、孔雀の羽根を使った作品を皆さんにいけていただきました。


今回の「いけばな動物園」、動物園を訪れた多くの方にいけばなを知っていただくよい機会だったのではないかと思います。いまだに「敷居が高い」「着物を着て正座でいける」というイメージも強いいけばなですが、実は自由で楽しいものなのだとお分かりいただけたのではないでしょうか。
また、いけばなをご覧いただくために久々に動物園を訪れたという方も、これをきっかけに、動物園の動物や各動物園のさまざまな取り組みに触れ、そこから自然界の動物や環境にも思いを馳せ、何かを考えるきっかけになれば、動物好きのいけばな人としてこんなに嬉しい事はありません。
ジャンルの違うもの同士がコラボをする事で、思わぬ発見や広がりが生じる可能性もあるかと思います。自分にとっても未知の世界であった今回のコラボイベントの中に、更に多くの方に動物や動物園の今を知っていただき興味を持っていただくためのヒントがあるかもしれません。
パフォーマンスの時に田村園長が「動物園もいけばなも、同じ『命』を扱うもの」という事をおっしゃっていたのが印象に残っています。命を思い、命に向き合い、これからも花をいけ、動物園に通い続けたいと思います。