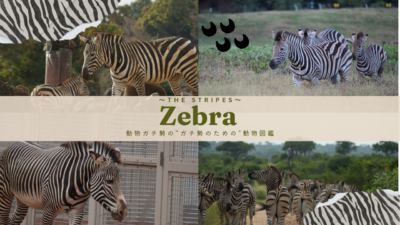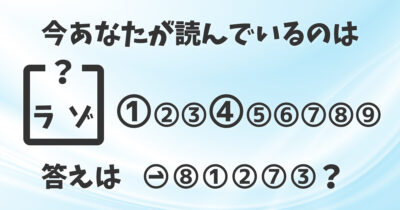動物園で会えるからこそ、もっと…
皆さんは動物園に行くとき、何かしら見たい動物を思い浮かべたり、口に出すことはないでしょうか?
アフリカゾウやジャイアントパンダのような人気者。
アムールトラやイリエワニといった捕食者。
カピバラやケープペンギンなどのかわいい動物。
しかし、それらはたいていの場合、多くの動物図鑑に載っていたり、普段は動物園に行かないという人でも知っているような有名な動物だと思います。
動物園には多くの動物たちが暮らしていますが、その中にはメディアで名前くらいしか聞いたことがないような動物や、動物に通な方しか知らないような動物も。ですが、彼らは視点を変えれば…
動物園で会えるからこそ、もっと知ってほしい動物なんです!
このシリーズではそんな動物たちについて「実はこんなところが面白い!」点も交えながら紹介します!
 Taisei
Taisei彼らを知れば、きっと会いに行きたくなります!
ヤブイヌ / Bush Dog


分類:食肉目 イヌ科 ヤブイヌ属
分布:ブラジル、コロンビアなど
南米の河畔林(川沿いの森林)やサバンナにペア、もしくは家族群で暮らすイヌの仲間です。
皆さんのよく知るイヌやオオカミとはかけ離れた短足、小さくて丸い耳、イタチを思わせるような顔立ちをしていますが……これでもイヌの仲間です!



最も原始的なイヌ科の一種とされています。
彼らは水辺を好み、指の間に水かきがついているため、泳ぐのも上手。
また、頻繁に鳴き交わすことで、見通しのよくない下生えの中でも連絡を取り合うことができるのです。
野生では、農地開発・プランテーションや牧草地への転換などによる生息地の破壊や、現地に持ち込まれたイヌからの感染症の伝播などによって個体数が減っており、ブラジルやペルーでは法律で保護の対象とされています。




動物園ではプールで水浴びをしたり、「ココ掘れワンワン!」と言わんばかりの穴掘りをするかわいらしい様子を見ることができますが、実は飼育下繁殖が難しく、日本では個体数が減りつつあります。
のいち動物公園(高知県)やよこはま動物園ズーラシア(神奈川県)では繁殖が試みられているようです。
メスのヤブイヌはマーキング(臭いをつけて縄張りを主張する行動)の際に、逆立ちします!
胴長短足な彼らにとって、逆立ちは高い位置にマーキングをするための工夫なのです。
シタツンガ / Sitatunga




分類:鯨偶蹄目 ウシ科 ブッシュバック属
分布:アフリカ南部・中央部
アフリカの湿地帯に暮らしているレイヨウ(アンテロープ)の一種です。
雌雄で外見に違いがあり、オスは灰褐色の体と湾曲したツノ、メスはオレンジ色でツノがないのが特徴。
夜行性で、単独かペア、小さな群れで生活します。
危険を感じると走って逃げるほか、潜水して目と鼻先だけを水面に出し、ワニなどの捕食者の気配が消えるまでやり過ごすという、まるで忍者の「水遁の術」のような行動も見られます。


動物園では、その華奢な体格からシカに間違えられていることが多いですが、実際にはウシの仲間です。
その証拠は、ツノが枝分かれしていないことや、その構造にあります!



私はシタツンガのいる動物園に行った時、「あれ、シカなのかな?」という声を聞くたびに、「この子たち、ウシなんですよ」と言ってます。
シタツンガの蹄は長く幅が広いため、体重がうまく分散し、地面がぬかるんでいる場所が多い湿地帯でも体が沈みません!
また、水辺を歩く時もほとんど音が立たないので、捕食者にも気づかれにくいのです。


ワライカワセミ / Laughing Kookaburra


分類:ブッポウソウ目 カワセミ科 ワライカワセミ属
分布:オーストラリア、タスマニア島
森林地帯から木がまばらに生えた草原まで、様々な場所で見られるカワセミです。
カワセミ科では世界で一番大きい種で、日本にいるカワセミと比較すると約3倍!
その名の通り、人間が大笑いしているかのような「ウハハハハ…」という独特な鳴き声をしているのが特徴で、これによって縄張りを主張し、外敵を寄せ付けないようにしています。
なお、雌雄は尾羽の色で見分けることができ、青がオス、褐色がメスです。



動物園では開園直後や閉園直前に鳴いていることが多いですよ。


実は、NHK「みんなのうた」で1962年12月から翌年1月にかけて流れた「わらいかわせみに話すなよ」という童謡があり、当時は幼かった世代の年配にもよく知られている鳥でもあります。
祖父母と暮らしている方は、ぜひ知っているかどうか尋ねてみてください!
ワライカワセミはカワセミの仲間でも、魚を食べることは稀です!
昆虫やネズミ、ヘビなど様々なものを食べ、時には他の鳥の巣を襲うこともあります。
アイゾメヤドクガエル / Dyeing Poison Dart Frog


分類:無尾目 ヤドクガエル科 ヤドクガエル属
分布:ガイアナ、スリナム、ブラジル、仏領ギアナ
南米の熱帯雨林に暮らす、美しい外見に反して毒を持つカエルであるヤドクガエルの仲間です。
体長は5cmほどと、ヤドクガエルの中では最大級。岩の間やコケの生えている場所を好み、水に入ることはほとんどありません。
メスは落ち葉の下などに一度に8~10個ほどの卵を産み、オスが孵化した幼生(おたまじゃくし)を背に乗せて、近くの水たまりまで運びます。
このようにオスが子守りをするのは、多くのヤドクガエルに見られる特徴です。



幼生を運ぶ時は、1~2匹ずつ乗せて、落とさないように慎重に運びます。パパは大変……


実は、ペットとして一般家庭で飼育されることもあり、日本にも輸入されているようです。
毒については生息地を同じくするアリやダニを食べることで貯めこむため、エサ用のショウジョウバエやコオロギを食べている飼育下個体は毒を持っていないとされています。
アイゾメヤドクガエルには様々なモルフ(体色のバリエーション)があり、上の写真のようなモルフは「アズレウス」と呼ばれています!
そちらはかつてはコバルトヤドクガエルという別種と考えられていました。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回紹介した以外にも、私たち動物園ガチ勢が皆さんに知ってほしい動物たちはまだまだいます!
というわけで、本投稿はシリーズ化します!
知っているようで知らなかった動物、一般イメージとは違う動物、実は身近な動物……
今後もそんな魅力にあふれた動物たちを紹介していきます!
次回をお楽しみに!