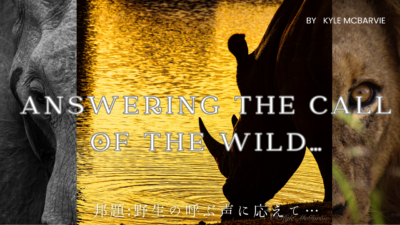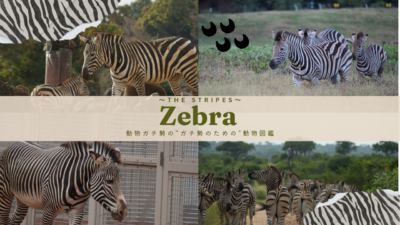近年、SNSやメディアの影響でマーモットへの関心が高まっています。愛らしい立ち姿や表情は確かに魅力的ですが、その背後にある保護の現状や飼育における責任について、私たちは正しく理解する必要があります。
マーモットとは何か

マーモットは、齧歯目リス科マーモット属(Marmota)に分類される動物の総称です。世界には約15種類のマーモットが存在し、主にアルプス山脈、カルパチア山脈、ヒマラヤ山脈、ロッキー山脈などの山岳地帯に生息しています。
主要な種類
- アルプスマーモット: ヨーロッパの高山地帯に生息

- ヒマラヤマーモット: アジアの高地に分布

- シベリアマーモット(タルバガン): 中国、モンゴル、ロシアの草原地帯

- バンクーバーマーモット: カナダ・バンクーバー島のみに生息する絶滅危惧種

- ボバクマーモット: 東欧の草原地帯
- ウッドチャック: 北アメリカに分布
ウッドチャック(別名グラウンドホッグ、学名 Marmota monax)はマーモット属に含まれるため、正真正銘のマーモットです。北米に広く分布し、最も分布域が広いマーモットとして知られています。一般的な「マーモット」と比べると森林や草地に適応しており、巣穴を掘って生活する習性も共通しています。
生態と特徴

マーモットは社会性の高い動物で、家族単位で暮らし、危険を察知すると甲高い警戒音で仲間に知らせます。種により異なりますが、年間の約6〜9ヶ月間は冬眠し、その前に体重を大幅に増やして脂肪を蓄えます。
マーモットと間違えやすい?似ている動物たち
マーモットの愛らしい姿に魅力を感じる方なら、きっと他の「丸くて愛らしい」動物たちにも興味を持つはず。ここでは、マーモットと見た目や生態が似ている動物たちを紹介します。
- ミーアキャット:アフリカの高度な見張りシステムを持つ肉食動物
- ケープハイラックス:見た目とは裏腹にゾウの親戚という驚きの系統
- ビーバー:人間以外で唯一環境を大規模改変する「森の建築家」
- プレーリードッグ:複雑な社会構造を持つが、日本では輸入規制のある要注意動物
- カピバラ:世界最大の齧歯類で「温泉好き」として愛される癒しの王様





それぞれが独自の進化を遂げ、異なる生態的役割を果たしています。「見た目の可愛さ」だけでなく、その動物本来の生態や保護状況を理解することが、真の動物愛につながるのではないでしょうか。
動物園でこれらの動物たちを観察する際は、それぞれの「生きる戦略」の違いに注目してみてください。きっと新たな発見と感動が待っているはずです!
マーモットの保護状況とワシントン条約
絶滅の危機に瀕する種
バンクーバーマーモットは、IUCNレッドリストで絶滅危惧IA類(CR)に指定されており、2000年代初頭には野生個体数がわずか22匹まで激減しました。保護活動により現在は徐々に回復していますが、依然として極めて深刻な状況にあります。

シベリアマーモットも毛皮目的の乱獲により生息数が激減し、IUCNレッドリストでEN(絶滅危惧IB類)に指定されています。

ワシントン条約による規制
ヒマラヤマーモット(Marmota himalayana)のインド個体群がワシントン条約(CITES)附属書IIIに掲載されており、該当地域からの国際取引には厳格な手続きが必要です。

バンクーバーマーモットはCITES未掲載ですが、カナダ国内法により厳格に保護されています。
ただし、CITES規制対象外の種であっても、これは決して
「自由に取引できる」ことを意味するものではありません。
日本におけるコツメカワウソ問題から学ぶ教訓
マーモットの保護を考える上で、コツメカワウソのペットブームが引き起こした深刻な問題を教訓として理解する必要があります。

日本が関与した絶滅危機の加速
- 2015〜2017年に東南アジアで押収された59頭の密輸カワウソのうち、32頭が日本向けでした
- 日本でのペットブームが密猟を促進し、野生個体数の減少に直接的に寄与
- メディアやSNSの影響で需要が急激に高まり、違法取引が横行
 うーぺー
うーぺーあくまで取締りで把握された個体数であり、実際にはそれ以上のコツメカワウソが輸入されていると考えられます。
ワシントン条約での規制強化
コツメカワウソは2019年にワシントン条約附属書Ⅰに掲載され、国際取引が原則禁止となりました。この背景には、日本をはじめとする消費国での需要増加が絶滅リスクを高めたという厳しい現実があります。


密輸の実態
カワウソの密輸では、親を殺して幼獣を奪い、キャリーバッグに詰め込んで運搬するという残酷な手法が用いられました。輸送中に死亡する個体も多数存在しました。
個人飼育の問題点
1. 入手経路の不透明性
マーモットの個人飼育における最大の問題は、入手経路の透明性が担保できないことです。
- 正規の輸入業者からの購入であっても、その個体がどこで、どのように取得されたかの追跡は困難
- 野生捕獲個体と繁殖個体の区別が困難
- 密輸や不正な取引による個体が市場に混入するリスク



「この個体は正規な手続きを経て輸入されました」と言われても、その真偽を個人が確認する術はありません。
2. 飼育環境の制約


- マーモットは社会性の高い動物で、単独飼育は本来の生態に反する
- 広大な屋外環境での群れ生活が自然な状態であり、室内飼育では根本的に不適切
- 冬眠の必要性や温度管理の複雑さ
- 広いスペースと特殊な環境設備が必要
- 巣穴を掘る本能的行動を満たす適切な土壌環境の確保
- 感染症法による輸入規制により、合法的な入手は極めて困難
3-1. 専門獣医師の深刻な不足と治療の現実
マーモットなどのエキゾチックアニマルを診察できる獣医師は極めて限られている上に、
「診察可能」と「適切な治療が可能」は全く別問題です。


- 獣医学部では犬・猫・産業動物が主で、エキゾチックアニマルの教育機会はほとんどない
- マーモットの専門知識を持つ獣医師は日本にほぼ存在しない
- 診察を断る動物病院も多く、緊急時の対応が困難
- 「マーモットを診る」と言っている獣医師でも、実際のマーモットに関する専門知識はほぼ皆無
最も深刻な問題は、お金を払って診察を受けても、適切な治療ができるわけではないことです。
動物園のように
- 24時間体制の専門スタッフ待機
- 治療費の制約なしでの最適な医療提供
- 継続的な健康管理と予防医療
- 蓄積された飼育・医療データの活用
- 他園や研究機関との情報共有
これらは個人飼育では絶対に実現不可能です。さらに、個人飼育では得られた医療経験が学術的知見として蓄積・共有されることもなく、将来のマーモット保護に寄与しません。
マーモットの医学的知見が乏しいからこそ、動物園や水族館などの公的機関で専門獣医師による系統的な研究・診療が行われることには意義が見出せます。これにより蓄積される医学データは、将来的な野生個体の保護や他の飼育個体の健康管理に直結する貴重な知見となります。
3-2. 高額な費用負担と継続飼育の困難性
日本国内でのマーモットに関する価格情報は企業・個人発信に限られ、公的統計は存在しませんが、一般的に100万円以上の高額な取引が報告されています。初期費用だけでなく、専門的な医療費や設備費も高額になります。
さらに深刻な問題は、長期飼育における社会的リスクです。
- 個人の経済状況悪化による飼育継続困難
- 飼い主の高齢化や病気、死亡による飼育放棄
- 民間施設の経営破綻による動物の行き場喪失
- 社会情勢の変化(パンデミック、経済危機等)による影響
公的動物園との決定的格差
- 動物園は自治体や公益法人による安定的な運営基盤
- 世代を超えた継続的飼育体制
- 経済的困窮による飼育放棄のリスクがない
- 社会情勢に左右されない公的使命としての動物保護
マーモットの寿命は種差がありますが、目安として10~15年(アルプス種では15~18年の報告あり)に及ぶため、個人や民間事業者の一時的な関心や経済力に依存する飼育は、動物の一生に対する責任を全うできない高いリスクを孕んでいます。
特に商業目的での飼育の場合、展示ができない病気や老化などがあった場合、経済的に終生飼育ができるかが疑問です。収益を生まない動物への継続的な投資は、営利事業では現実的に困難であり、動物の使い捨てや安楽死という最悪の結果を招く危険性があります。
動物園の場合は、民間では難しい高額な治療やその経過の記録など、命を最後まで無駄にしないことが期待できます。展示価値を失った高齢動物や病気の動物に対しても
- 経済的制約のない終生飼育
- 最新医療技術による治療
- 症例記録の学術的蓄積
- 剖検による死因究明と知見蓄積
- 次世代への経験継承
これらは公的使命を持つ動物園だからこそ可能であり、一つ一つの命が将来の保護活動に確実に活かされるシステムです。
動物園におけるマーモット飼育の意義


現状:日本国内でのマーモット展示
現在、日本動物園水族館協会(JAZA)加盟園でマーモットを飼育展示しているのは以下の施設です
- 伊豆シャボテン動物公園:ボバクマーモット3頭(モンベル、パタゴニア、コロンビア)を飼育
- 那須どうぶつ王国:2025年4月17日よりウッドチャック4頭の一般公開を開始
動物園飼育への肯定的評価
獣医学の発展に寄与
動物園での飼育は、専門獣医師による継続的な健康管理により、マーモットの医学的知見を蓄積し、将来的な保護活動に活用できる貴重なデータを提供します。
研究・教育拠点としての役割
動物園は大学や研究機関と連携し、マーモットの生態や行動に関する科学的研究を実施できる唯一の場です。これらの知見は野生個体の保護戦略立案に不可欠です。
種の保存における重要性
現在、日本の動物園ではマーモットの組織的な繁殖計画は存在しません。伊豆シャボテン動物公園の3頭は全てオスであり、繁殖による種の保存には寄与していないのが実情です。
しかし、将来的にマーモットの保護が必要になった場合を考慮すると、新個体の導入に対して極端に否定的になることは問題があります。動物園が種の保存という重要な役割を果たすためには、適切な管理と倫理的配慮の下で、必要に応じて新血統を導入できる柔軟性が求められます。既存の個体のみに依存していては、動物園の本来の保全機能が制限される可能性があるのです。


倫理的ジレンマと未来への責任
野生動物の「人間の都合」への組み込み
動物園での飼育であっても、現地で生息していた野生個体を捕獲して人間の都合に合わせて管理することに変わりはありません。この現実を軽視すべきではありません。
必要な配慮と姿勢
- 彼らの生命と生活への深い敬意
- 単なる展示や研究対象としてではなく、一つの尊い生命として向き合う姿勢
- 得られた知見を確実に野生個体の保護に還元する責任
- 未来世代への環境保全責任の認識
日本の現状


日本のテレビやメディアにおける動物の扱われ方は、いまだに「かわいい」「面白い」といった娯楽的側面に偏っているのが現状です。
確かに有意義なドキュメンタリーも増えつつありますが、依然としてバラエティー番組で安易にエキゾチックアニマルを取り上げる傾向が目立ちます。こうした放送が視聴者の興味を引き、将来的に正しい知識を学ぶきっかけになる可能性もありますが、現実的には衝動的な飼育ブームを誘発しやすく、実際にコツメカワウソのペットブームがその典型例となりました。
私たち一人一人ができること
1. 正しい知識の習得
- マーモットの生態や保護状況についての理解
- エキゾチックペット問題の構造的理解
- 「かわいい」の背後にある現実への認識
2. 責任ある選択
- 安易な個人飼育の回避
- 動物園や適切な施設での観察を選択
- SNSでの無責任な拡散を控える
3. 保護活動への支援
- 信頼できる野生動物保護団体への寄付
- 環境保全活動への参加
- 現地保護プロジェクトの支援
4. 消費者としての責任
- 適切な許可と管理下にある施設を支援
- 出所不明な動物の取引に関与しない
- 問題のある業者や施設を利用しない
まとめ:持続可能な共存に向けて


マーモットの魅力に惹かれること自体は自然な感情ですが、それをどのように表現し、行動に移すかが重要です。
個人飼育は、入手経路の不透明性、専門医療の不足、適切な飼育環境の確保困難性から、強く批判されるべきです。一方で、適切に管理された動物園での飼育は、教育・研究・種保存の観点から意義があると言えるでしょう。
ただし、動物園での飼育であっても、野生動物の生命と尊厳を最大限尊重し、得られた知見を確実に保護活動に還元する責任があることを忘れてはなりません。
私たちに求められているのは、マーモットを含む野生動物との持続可能で倫理的な関係の構築です。短期的な感情や欲求ではなく、長期的な視点での環境保全と種の保護を最優先に考えることが、真にマーモットを「愛する」ことにつながるのではないでしょうか。
マーモットに限らず、エキゾチックアニマルの個人飼育は法律の範囲内であれば可能であり、そのすべてが密輸に基づくものではありません。高額な費用を払い、自らの判断で飼育している以上、病気の際に治療するか否かも飼い主の考え方に委ねられる部分があり、他人が一方的に口を出すことはできないでしょう。
一方で、「守りたい」と思う気持ち自体も人間のエゴかもしれません。それでも私は、マーモットをはじめとする野生動物を守りたいと考えます。そのために、医学的知見や飼育経験が積み重ねられる動物園での飼育には大きな意義があると肯定的に捉えています。
もっとも、「そもそも自然から動物を連れてくるべきではない」という立場もまた筋が通っており、その場合は医学的研究さえ不要だという意見も理解できます。
結局のところ、完全な正解は存在しません。ただ一つ確かなのは、私たち人間がどう向き合うかによって、マーモットを含む野生動物の未来が左右されるという事実です。その責任を意識し、矛盾や葛藤を抱えながらも、より良い共存のあり方を模索し続けることこそが重要なのではないでしょうか。



皆様の投稿お待ちしております。
参考情報
- IUCN Red List of Threatened Species
- ワシントン条約(CITES)関連資料
- WWFジャパン「コツメカワウソ保護」報告書
- 日本動物園水族館協会「種の保存」関連資料
- 伊豆シャボテン動物公園公式情報
- 那須どうぶつ王国公式情報
- 株式会社N Life’s プレスリリース(ヒマラヤマーモット輸入関連)