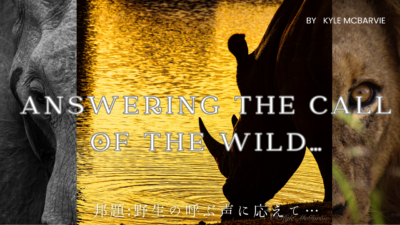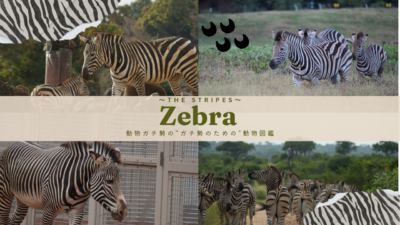はじめに
 Toki
Tokiこんにちは!マレーシア在住のTokiです!
「カワウソの飼育を考える」後編です。
前編の記事はこちら↓


前編の記事では、日本で飼育されているカワウソの紹介や、コツメカワウソについて、そして現在日本で飼育されているコツメカワウソの環境をお伝えしてきました。
後編の今回はこのような流れでコツメカワウソの飼育について考えていきます:
1-1 コツメカワウソの餌
1-2 餌と尿路結石の関係
1-3 コツメカワウソの給餌方法
2-1 展示場の広さ
2-2 巣箱について
2-3 水場について
3-1 ふれあいアクティビティ
3-2 コツメカワウソの為にできること
下記の飼育ガイドラインを基に解説します。より詳しく知りたい方は、直接ガイドラインを読んでみてください。
日本動物園水族館協会 適正施設ガイドライン 【コツメカワウソAonyx cinerea】
・JAZA(日本動物園水族館協会)が推奨しているガイドライン
・BIAZA(イギリス・アイルランド動物園水族館協会)が作成し、日本アジアカワウソ保全協会が和訳したガイドライン
Summary of Husbandry Guidelines for Asian Small-clawed Otters in Captivity
・IUCN(国際自然保護連合)が作成したコツメカワウソの飼養管理のためのガイドライン
・IUCN(国際自然保護連合)が作成したコツメカワウソの最低限の飼養管理と動物福祉ののためのガイドライン
・AZA(アメリカ動物園・水族館協会)が作成したカワウソの飼養管理ガイドライン
1. コツメカワウソの食生活


まずはコツメカワウソの食生活から見ていきましょう。
コツメカワウソは基礎代謝が高い動物で、体重の約20%に相当する量の餌を毎日摂取する必要があります。消化の速度が非常に速く、食べたものにもよりますが摂取から排泄までにかかる時間は1~2時間程度です。このため、野生のカワウソは1日の40%~60%を採食の為に使っています。
1-1 コツメカワウソの餌
では、コツメカワウソの基本的な餌の内訳を見ていきましょう。
ガイドラインを作成した団体により内訳が異なりますので比較してみます。いずれの団体も、年齢や飼育環境等により餌の調整が必要とし、餌のバリエーションの変更や栄養剤の追加の必要性を明記しています。
BIAZA(イギリス・アイルランド動物園水族館協会)が推奨する餌の内訳です。
| 割合 | 内容 | 例 |
| 50〜60% | 甲殻類/二枚貝/無脊椎動物 | ザリガニ、エビ、ムール貝等 |
| 30~40% | 魚類 | ドジョウ等(脂肪の少ない魚) |
| 10〜20% | 多品目 | 野菜、ナッツ、卵、肉等 |
AZA(アメリカ動物園・水族館協会)が推奨する餌の内訳です。
| 割合 | 内容 | 例 |
| 54.5% | ネコ用缶詰フード (尿石の発生を抑制するもの) | Hill’s x/d、 IAMS Moderate pH/O |
| 24.6% | キュウリウオの仲間 | |
| 17.4% | カラフトシシャモ | |
| 2.5% | ネコ用乾燥フード (尿石の発生を抑制するもの) | Hill’s x/d、 IAMS Moderate pH/O |
| 1% | 昆虫 | コオロギ、ミルワーム等 |
IUCN(国際自然保護連合)が推奨する餌の内訳です。
| 割合 | 内容 | 例 |
| 70〜80% | 肉類 | 牛肉、鶏肉、IAMSキャットフード等 |
| 20〜30% | 淡水魚 | 脂身の少ない魚 |
| 随時 | その他 | ザリガニ、ヒヨコ、ミルワーム等 |
団体によりかなりの差があることがわかりますね。この差は何故発生するのでしょうか?各団体のガイドラインを読んでいくと、その理由が少しづつ見えてきます。
- BIAZAは、イギリス内のコストや調達性を考慮した現実的な献立です
- AZAは 管理された施設での餌の安定性と健康維持を最優先にした献立です
- 自然保護団体であるIUCNは、できるだけ野生の食性を重視した献立です
このように、各団体の推奨する餌の献立は異なるので、園館ごとにガイドラインものを参考にしながら合うものを作っているのでしょう。
1-2 コツメカワウソの餌と尿路結石
飼育下のコツメカワウソにおいて、最もよく見られる健康問題が尿路結石だと言われています。これは腎臓や尿道などの尿路に、結晶が集まって結石ができる病気です。進行すると、尿管閉塞によって急性腎不全になり、死亡するケースもあります。
2018年のYoongらによる研究によると、回答のあった飼育個体のうちAZAでは62.8%、アジアの園館では9.4%に結石ができていたとの結果が出ています。
北米中心のAZAと比べてアジアの園館において結石が発生しにくい理由は詳しくは不明ですが、飼育環境や年齢などの総合的な理由が影響しているとみられています。
結石の防止には餌の献立が大きな要因とされており、この研究では下記のようなアドバイスをしています:
- 餌のカルシウム量の減少
- タンパク質とナトリウムの適度な増加
- 魚類・甲殻類を中心とした、野生の餌に近い食事を推奨
餌の他にも、清潔な水への十分なアクセスや運動量も関係あり、生活環境の改善や定期健診等でリスクの減少は可能とされています。
更に詳しく知りたい方は、こちらの研究をご覧ください:
Urolith Prevalence and Risk Factors in Asian Small-clawed Otters (Aonyx cinereus)
和訳:コツメカワウソ(Aonyx cinereus)における尿路結石の有病率とリスク因子
1-3 コツメカワウソの給餌方法
先述したとおり、コツメカワウソは消化の速度が非常に速い動物で、主食となる肉や魚です。これらのことから、給餌は一日に数回に分けて常に状態の良い餌を提供するのがベストとされています。
また、展示場内での行動の単調化や、餌を探すことに時間をかける野生本来の行動に近づけるために、このような給餌方法が推奨されています:
- 餌を展示場内に分散させ、動物に探させる
- 一部の餌を水に投げ入れる
- 氷やエンリッチメントの道具などに餌を入れ、取り出す工夫をさせる
下記は、BIAZAによる飼育ガイドラインに例として挙げられているHertfordshire Zooでの給餌スケジュールの例です。量は1頭当たりです。
| 曜日 | 朝食 8時前後 | 昼食 11時前後 | おやつ 13:30 | 夕食 16時前後 |
| 月曜日 | ドジョウ 430g ひき肉 80g Aquaminivit タラの肝油 | マウス 4匹 マテガイ 16匹 野菜 80g クエン酸カリウム | ザリガニ 270g | エビ 140g 野菜 80g |
| 火曜日 | マス 430g ひき肉 80g Aquaminivit | ヨーロッパミドリガニ 100g ムール貝 100g 野菜 80g | ザリガニ 270g | 小エビ 140g 野菜 80g |
| 水曜日 | ドジョウ 430g ひき肉 80g Aquaminivit | エビ 160g ミールワーム 60ml 野菜 80g | ザリガニ 270g | ヨーロッパミドリガニ 140g 野菜 80g |
| 木曜日 | ドジョウ 430g ひき肉 80g Aquaminivit タラの肝油 | マウス 4匹 ムール貝 80g 野菜 80g クエン酸カリウム | ザリガニ 270g | ヤドカリ 4匹 マテガイ 4匹 野菜 80g |
| 金曜日 | ドジョウ 430g ひき肉 80g Aquaminivit | ヤドカリ 4匹 エビ 160g 野菜 80g | ザリガニ 270g | 小エビ 140g 野菜 80g |
| 土曜日 | ドジョウ 430g ひき肉 80g Aquaminivit タラの肝油 | マウス 4匹 ヨーロッパミドリガニ 80g 野菜 80g | ザリガニ 270g | マテガイ 4匹 ザリガニ 110g 野菜 80g |
| 日曜日 | ドジョウ 430g ひき肉 80g Aquaminivit | ヤドカリ 4匹 小エビ 160g 野菜 80g | ザリガニ 270g | ムール貝 140g 野菜 80g |
Aquaminivitとはビタミン・ミネラルのサプリメントです
上記のほかに、1日2回の不規則な時間に展示場内に”ばらまき給餌”を実施。1回1頭につき80gで、内容はニンジン、リンゴ、サツマイモ、洋ナシ、トマト、ブルーベリー、カボチャ、スナップエンドウ、サヤインゲン、セルリアク、黄ピーマン、ブロッコリー、カリフラワー、ゴキブリ、コオロギ、バッタなどから野菜を主体に与えています。
このように、栄養価を考慮したうえでなるべくバラエティー豊かな餌を与えることが望ましいとされます。カワウソのストレス軽減のため、給餌時間に関しては完全にランダムか完全に固定かのいずれかが好ましいとされています。
入手可能な食材や日没の時間などにより状況は異なりますが、日本国内の飼育施設においてもなるべく似たようなスケジュールでの給餌が理想とされます。
2. コツメカワウソの展示環境
ここからは、コツメカワウソの展示環境について見ていきましょう。
2-1 展示場の広さ
BIAZAとIUCNは、展示場の広さについて共通の数字を推奨しています。その広さとは、1ペアの飼育で60㎡、1頭追加ごとに5㎡です。JAZA加盟館の展示場の広さはは2.85~490.3㎡で、平均が44.82㎡です。この数字を見ると、世界的な基準と比べて日本の展示場がいかに狭いかがわかりますね。
いずれの団体も、コツメカワウソの社交性の高い生態を考慮し、単独飼育は推奨していません。
具体例を見てみましょう。こちらは台湾の臺北市立動物園のカワウソ展示場。園内に4カ所あるカワウソ展示場はいずれも国際ガイドラインを大きく上回る広さを備えており、家族を中心とした群れまたは繁殖や目的としたペアで飼育されています。


こちらの展示場では15頭ほどのカワウソが群れで生活していました。社員に写っているのは展示場の約半分です。


こちらはペアの展示場。画像の中央右側に写っているコツメカワウソ2頭と比較すると、展示場の広さが伝わります。なお、展示場は広すぎて写真に納まっていません。


臺北市立動物園ではこの他にもテナガザルとの混合展示なども行っており、いずれも非常に広い展示場で活発に動くカワウソに会えます。
2-2 巣箱について
カワウソのシェルターとなる巣箱に関しては、BIAZAとIUCNは展示場内の設置について強く推奨しています。カワウソ1頭につき巣箱1つに加え、更に群れの全頭が入ることができる大き目の巣箱の設置が推奨されています。巣箱のサイズに関してはJAZA含め共通の認識を推奨サイズがあり、1頭用の巣箱に関しては長さ60cmx幅60cmx高さ50cmで、入口はおよそ15cm x 15cmが望ましいとされています。
しかしながら、JAZAのデータを見てみると、展示場に巣箱があるのは全体の51%にすぎず、約半数の展示場は巣箱がない状況です。IUCNのガイドラインでは“絶対に巣箱に入れない状況を作ってはいけない”と強く書いてあるにも関わらず、です。
カワウソのストレス飼育環境改善のため、今後は各園の認識が改まり、必要数の巣箱の設置と常時開放が望まれます。
2-3 水場について


ここからは、水場の環境を見ていきましょう。水辺に棲むカワウソにとって水場は非常に重要です。
まず、陸場と水場の割合を見てみましょう。コツメカワウソは水場が必要なものの、常に水に浸かっているわけにもいきません。体を乾かしたり、歩き回る陸場も必要です。各団体の推奨する割合を見てみましょう。
| 団体 | 陸場の割合 | 水場の割合 |
| BIAZA | 70〜80% | 20〜30% |
| IUCN | 80% | 20% |
| AZA | 83〜86% | 14〜17% |
AZAに関しては上記割合の水場に加えて浅いプールを用意するよう推奨しています。それを踏まえてまとめると陸場80%前後が推奨されていることがわかります。
仮に4匹のカワウソを最小限の70㎡の広さで飼育した場合、約14㎡の水場が必要になります。
JAZAに関してはAZAに従っていますが、加盟園館の平均比率は陸場67%水場33%であり、水場の面積が少し多いです。これは、日本が他国と比較して水族館の数が多く、展示の方法として水場が増えていることが由来とも考えられます。
では、水深はどうでしょうか?水深に関して具体的な数値を出しているのはAZAのみで、加盟園館の水場の深さは50~140cmとされています。また、各団体共通で、水場の入口は必ずスロープなどで段階的に深くなるような調整を行い、カワウソが好む水深10~20cmの浅場を設けるよう推奨しています。
カワウソにとっての水場の重要性がわかりますね。残念ながら一部の園館で見かける、水をはったタライ等で水場の代用はできないということです。
3. カワウソと人とのかかわり
3-1 ふれあいアクティビティ


コツメカワウソはその人気から、動物園や水族館で様々なイベントに参加しています。餌やり、ふれあい、ショーへの参加など内容は様々ですが、それらへの参加はカワウソにとって良い環境なのでしょうか?
まず、来園者の存在がカワウソにとってどのような影響を与えるのか見てみましょう。
こちらに関しては様々な調査結果が出ており、一概に良いとも悪いとも言えません。イタリアのAcquario di Cattolicaで行われた調査ですと、開館日は休館日と比べてカワウソが目視できる場所に来る時間が減り、個体同士の遊びなどの自然な行動も減ったと報告されています。これは、来園者の存在がカワウソに対してストレスを与えている可能性があると考えられます。しかし、イタリアのGiardino zoologico di Pistoiaで行われた調査では、飼育員への餌の要求を除き、人の有無によるカワウソの行動への変化はなかったと報告されています。
この2つの調査はいずれも小規模な物であり、結論としては来園者の存在によるストレスは個体や環境によるとしか言えず、個体によって大きく異なるようです。イベントなどでカワウソが来園者と接近する場合は、ストレスを感じにくい個体の選定が求められます。
これらの調査に関して、更に詳しく知り方はこちらをご確認ください:
和訳:カトリカ水族館における 3 頭のコツメカワウソ(Aonyx cinereus)の行動に対する来館者の影響
和訳:飼育下のコツメカワウソペアにおける環境条件と人間の存在が行動に及ぼす統合的影響
では、来園者による餌やりなどはどうでしょうか?
カワウソと直接触れることのできるイベントなどは、様々なリスクが伴うとされています。
狩りをする捕食者であるカワウソは、鋭い爪や歯を持ち、まれではありますが人を襲って怪我をさせる例が世界各地で発生しています。主に野生個体の例ですが、飼育個体であってもいつ事故があってもおかしくありません。園館で”カワウソと握手”などのイベントを行う際は、ルールの説明やスタッフの付き添いなど、安全面の十分な配慮が必要です。
2025年8月現在、日本の園館で確認されているふれあいイベント等に参加している種は、伊勢シーパラダイスのツメナシカワウソを除き全てコツメカワウソです。この2種は他種のカワウソと比べて爪が非常に短いですが、100%安全だということではないので注意が必要です
また、カワウソとの過度なふれあいの際の写真が、本来の意図とは異なる方向でSNS等で拡散される例も多いとされています。園館でカワウソと接近するイベントは、本来であればカワウソについてよりよく知ってもらい、保護活動につなげることを目的としています。しかしながら、至近距離でカワウソと接している写真がSNS等で”映える”と認識され、結果的にカワウソが簡単に飼育できる動物だと誤認されるようなケースも多く見られます。
アニマルカフェなどの施設での過度な接触は海外のニュース等でも問題視されており、本来保護すべき動物とどこまでのふれあいを行うべきなのか、今後のルール作りが望まれます。
IUCNでは、誤解を招く例を作らないために、園館に対してこのような写真を共有しないよう推奨しています:
- スタッフとの直接接触の禁止
- カワウソを直接持つ、手で餌を与える等の行為は医療ケアの以外では禁止
- 接触する場合は手袋などの防具を付け、飼育員とわかるような服装で行う
- 優しく拘束している様子のみを共有すること
- 来園者との直接接触の禁止
- カワウソと来園者の直接接触は行わないこと
- 来園者による餌やりは必ずバリア越しに行い、トング等を使用し、制服を着た飼育員の監督下で行うこと
- 情報の開示
- 医療目的でカワウソに接触する場合、行為の説明や共有の目的を明確に示すこと
- キャラクター化の禁止
- 服を着せる、赤ちゃん用おもちゃを使う、適切でない食べ物を与える等を行わないこと
これはリストの一部です。更に詳しく知りたい方はこちらからご覧ください:
Best Practice Guidelines for Responsible Images of Otters
和訳:カワウソ画像の責任ある取り扱いに関する優良実務指針
このようなガイドラインが今後日本でも普及し、”カワウソは安易に飼える動物ではない”というメッセージがしっかり伝わるようになってほしいですね。カワウソのイベントをただ”かわいい”だけでは終わらせず、教育や保護に繋がるよう責任を持った実施やSNSでの共有が求められるでしょう。
3-2 コツメカワウソの為にできること
お伝えしたように、コツメカワウソは絶滅危惧種です。そして、この状況になってしまった理由には、私たち日本人も関わっています。コツメカワウソの未来のために、何ができるか考えてみましょう。
私たちができることは決して難しいことばかりではありません。
まず、コツメカワウソを含む野生動物の生息地を守るため、環境保護に関心を持ち、行動することが大切です。河川や湿地、マングローブ林など、カワウソの暮らす自然環境は年々失われています。私たち一人ひとりが環境保全の意識を持つことで、その速度を少しでも緩めることができます。
また、違法に捕獲された動物や密輸された個体を「ペット」として飼わないことは非常に重要です。かわいらしい姿に惹かれてしまう気持ちは理解できますが、その裏には、親から引き離され命を落とす子どもたち、過酷な輸送で傷つく動物たちの現実があります。需要がある限り、違法取引は止まりません。「買わない」ことは、違法取引をなくす最も効果的な方法の一つです。
さらに、動物園や水族館、観光施設での展示やふれあい体験についても、私たちが慎重に選択する必要があります。適切な飼育環境や福祉に配慮した施設を支持し、そうでない施設には行かないという消費者としての意思表示が、業界全体の改善につながります。
そして、身近な人たちにこうした問題を伝え、共に考えていくことも大切です。SNSでの発信や学校・地域での啓発活動など、私たちの声は小さくても、積み重なれば大きな力になります。
カワウソの保護活動についてより強く関わりたいと思っている方は、下記のような団体の支援も検討してみてはいかがでしょうか?
アジアに生息するカワウソの調査・研究、普及啓発、学術交流を通じて、絶滅を防ぐ努力を続けています。活動報告や寄付・入会の案内も公式サイトに掲載されています。
コツメカワウソの違法取引問題や法制度の改善を提言し、流通状況の監視や調査結果の公表にも取り組んでいます。密輸状況に関する専門誌への報告も行っています。
コツメカワウソは、私たちの世代の選択と行動によって、未来に残せるかどうかが決まります。今この瞬間にも、野生の個体数は減り続けています。「かわいいから好き」で終わらせず、「守りたいから行動する」存在として、コツメカワウソと向き合っていきましょう。
おわりに


いかがでしたでしょうか?
前後編に渡り、カワウソの飼育環境の現状や理想を見てきました。
さて、“カワウソを自宅で飼いたい”と言う方は残念ながら未だに一定数います。しかし、この記事を読んだ後でも同じ気持ちでしょうか?
冒頭に書いた、カワウソを飼いたい方から聞く言葉を回答と共にをふりかえってみましょう。
- 小さい動物だし、家でも飼えるよね?
- 単独飼育は不可、最低でも2匹での飼育
- 広さは最低60㎡
- 水場は最低12㎡で深さは最低50cm
- ペットショップにはいないけど、専門店に行けば買えるよね?
- 絶滅危惧種に指定されており、一般販売はされていない
- 出所不明の密輸された可能性の高い個体が多数流通している
- 適切な方法以外での入手は違法
- 餌はキャットフードで良いよね?
- 魚、肉、野菜など多様な献立の餌に加え、専用の栄養剤等が必要
- 消化が速いため、おやつを含め日に数回の食事が必要
- 尿路結石になりやすく、高度な食事の調整や健康管理が必要
カワウソを飼育するためには、紹介したように非常に大きなスペースを必要で、餌、健康管理、エンリッチメントなどに関しても専門知識に加え非常に多くの時間、費用、手間がかかります。これは一般家庭で到底用意できるものではなく、犬や猫を飼う感覚て飼える動物ではありません。
カワウソはペットとしては飼えない動物なんです。
この記事の一番の目的は、読んでいただいた方にこの事実を再度認識してもらい、広めてもらうことです。
飼育下でのカワウソ達が可能な限り理想に近い環境で今後も健康に過ごし、それを見た人々が野生のカワウソが置かれている現状を知ってもらえれば良いなと思っています。
余談
最後までお読みいただきありがとうございます。ここからは、ちょっとした余談です。
実はカワウソは、私にとって色々と縁のある動物なんです。幼少期を主に過ごしたマレーシアでは家の前の干潟で頻繁に野生のカワウソを見ていまして、もはや日常の一部でした。幼かった私は、カワウソはマレーシアではどこにでもいる動物だと思っていました。
日本の大学に進学後、国内のカワウソ研究の権威である恩師の下で学びながら、夏休みなどでマレーシアに戻る際は野生のカワウソを探す日々を送っていました。


こちらは当時よく訪問していた海岸。砂浜の奥に干潟が広がり、多くのカワウソや渡り鳥が過ごす場所でした。


当時よく見られたビロードカワウソ。動物園では見られない、野生本来の姿を間近で観察できました。


水深は浅いようでしたが、魚類を起用に捕獲していました。こちらはナマズの仲間。他にも、カニなどの甲殻類をの捕獲する姿も頻繁に観察できました。


こちらは2025年現在の同じ場所です。開発が進むにつれ干潟は全て埋め立てられ、生き物たちは姿を消しました。現在カワウソ達は、10キロ以上離れた国立公園周辺で確認されていますが、当時と比べて数が減り、観察するのはとても難しいです。また、”魚を食べる”という理由から地元の漁師に嫌われ、安全な住処を追われている状況です。
カワウソの個体数減少となっている主な要因は密猟と環境破壊。この両方を対策していかなければ、今後カワウソの個体数は減少し続け、絶滅してしまった二ホンカワウソと同じ運命を辿るかもしれません。
この記事を読んで、カワウソたちの現状や今直面している問題について、ほんの少しでも知ってもらえたら嬉しいです。そんな小さなきっかけが、いつか彼らを守る行動につながっていくことを願っています。