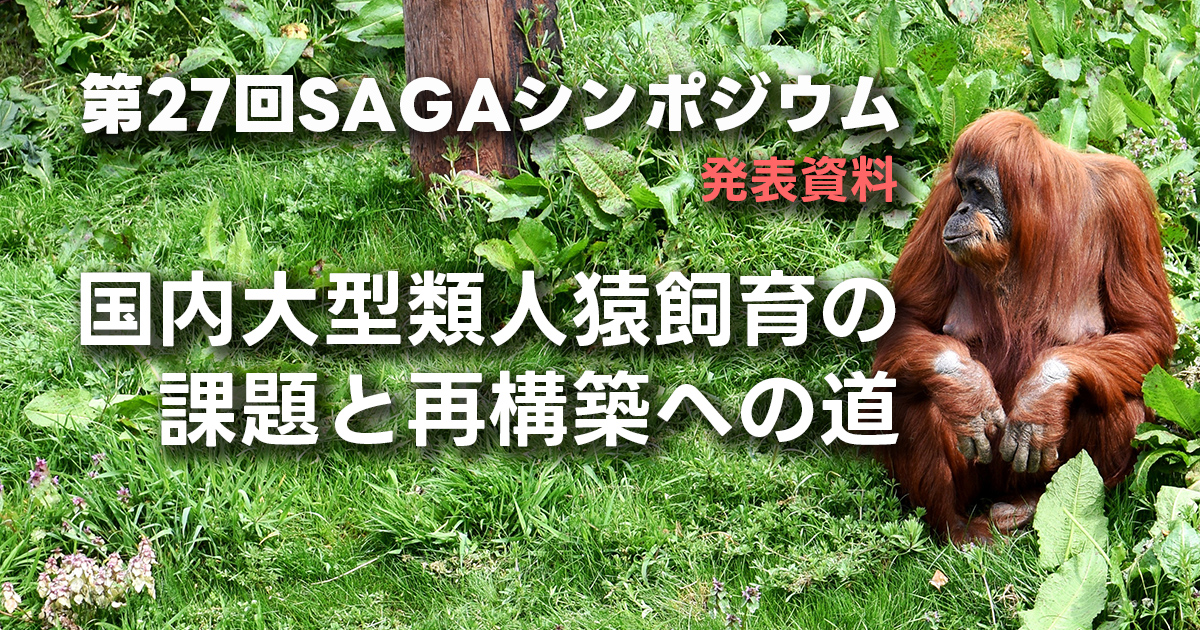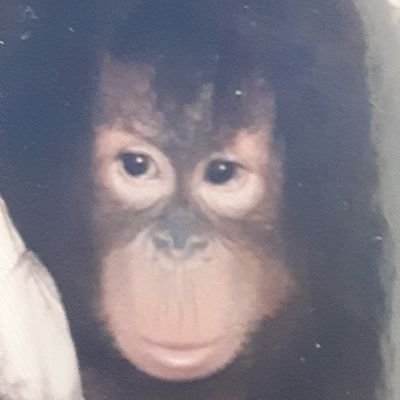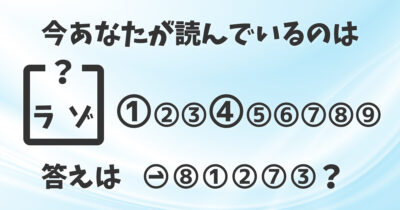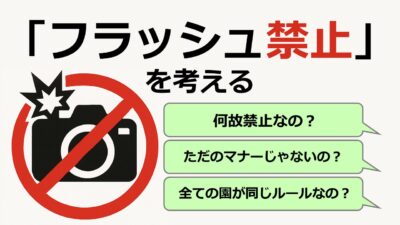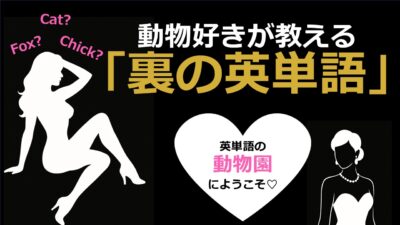大型類人猿の飼育に携わっていた私が経験より強く感じていた事をお伝えします。

直接飼育から準間接飼育への移行に伴い、大型類人猿と飼育員との心理的距離が変化し、これまで培われてきた飼育の経験値が、世代間で十分に継承されず失われた点が大きな課題であると感じています。
また、欧米の飼育マニュアルには基本的な指標は示されているので、国内の動物園ではそれも参考として飼育が行われていると思いますが、飼育個体の成育歴や飼育環境の違いに関する分析が不充分なため、現場での適切な判断が行えていない点も見逃せないと思います。
飼料管理については、以前より大きく改善されていると感じますが、心理的ケアや行動管理においては、なお一層の取り組みが求められると考えます。
大型類人猿とは、ボノボ、チンパンジー、オランウータン、ゴリラを指します。
第1章:準間接飼育がもたらした変化とその影響

1-1 安全性の向上と引き換えに
準間接飼育(Protected Contact)は、飼育員の安全を確保する大きな転換点でした。しかし、物理的な隔たりが飼育員と動物の相互理解に壁を作り、細やかな観察力や直感的な対応能力を育みにくくしてしまっています。
準間接飼育とは、飼育員が柵や壁越しに動物と接し、餌やりや健康管理を行う飼育方法です。直接的な接触を避けつつ、飼育員の安全を確保することを目的としています。
1-2 経験知の断絶と継承不全
かつてのベテラン飼育員は、動物の仕草や雰囲気から状態を読み取る「暗黙知」を持っていました。こうした知識は言語化が難しく、マニュアルには落とし込めません。
世代交代とともに、その経験が組織から失われ、現場では「感じ取る力」が希薄になりつつあります。
暗黙知とは
大型類人猿の飼育においては、マニュアルや日誌だけでは伝えきれない「暗黙知」が非常に重要な役割を果たします。これは、長年の観察と経験を通じて飼育担当者が身につける”勘”のようなものであり、動物のわずかな変化や空気感を敏感に察知する力です。
たとえば、日誌に「朝の餌の食いつきが悪かった」「鳴き声が少なかった」と記録されていても、それが通常の範囲内の変化なのか、何らかの異変の前触れなのかを見極めるには、その個体や群れの”普段の様子”を深く理解している必要があります。そうした判断は、数値や言葉では表しきれない、ごく微細な行動や雰囲気の違和感を察知する力に基づいています。
この感覚は、人間同士の関係における「なんとなく今日は機嫌が悪そう」といった直感に近いものです。明確な根拠はなくても、日々の接触を重ねる中で自然と培われていく感受性であり、大型類人猿のように知性と感情の豊かな動物を扱う上では欠かせない要素となります。
そのため、このような暗黙知を次世代の飼育者にどのように継承し、共有していくかは、現場における大きな課題の一つです。記録や口頭での申し送りだけでは限界があるため、実際に一緒に観察し、動物と向き合う時間を重ねる中で、少しずつ”感覚”として身につけていく必要があります。
第2章:マニュアル依存の限界

2-1 欧米式マニュアルの導入と効用
JAZA(日本動物園水族館協会)やAZA(アメリカ動物園水族館協会)、EAZA(ヨーロッパ動物園水族館協会)が提供するマニュアルは、科学的根拠に基づく最低基準として機能し、特に栄養や展示施設の設計に一定の成果を上げています。
2-2 現場との乖離と判断力の低下
マニュアルは「守るべきルール」ではなく「現場に適応させるための指針」であるべきです。日本特有の気候、施設制約、個体ごとの違いを無視した運用は、かえって動物の福祉を損なうリスクを高めています。
2-3 文化的背景による動物観の違い
欧米では牧畜文化の中で、動物をトレーニングし管理することが日常的な感覚として根付いています。家畜を導き、制御することが生活の一部であったため、動物に対して指示を与え、行動を形成していくことに抵抗がありません。
一方、日本では農耕文化を基盤とし、自然との共生や調和を重んじる価値観が育まれてきました。動物に対しても「従わせる」よりは「寄り添う」姿勢が強く、積極的な介入には慎重になる傾向があります。
このような文化的背景の違いが、海外で作成されたマニュアルを日本の現場に適用する際の認識のズレを生む一因となっています。海外から動物を導入する際にも、この文化差を理解した上で、日本の飼育現場に合った方法を模索していく必要があります。
第3章:進歩と課題が混在する福祉管理

3-1 栄養管理の改善
飼料の改善に関して、私は特定の果物――たとえば「バナナは与えてはいけない」といった個別の制限を設けることよりも、飼料全体の栄養バランスを重視すべきと考えています。
特に、大型類人猿に与える飼料の構成においては、野生下での食性を踏まえ、野草や樹木などの割合を適切に含めることが重要です。現代の果実は品種改良によって糖質が高く、嗜好性も強いため、過剰に与えることで本来必要な繊維質やミネラルの摂取が不足し、栄養バランスの崩れや偏食、さらには健康や行動面への悪影響を招く恐れがあります。
そのため、問題は特定の果実の可否ではなく、糖質の多い果実類の給餌量を適正化し、動物本来の食性に沿った給餌内容に見直していくことにあると考えています。
ポイント:食材の国際的な違い
前章で述べたマニュアルの課題にも関連しますが、同じ果物や野菜でも、国や地域によって栄養価や味、見た目に大きな違いがあることは重要な点です。
たとえば、熱帯地域の動物園では、飼料として利用する植物は気候の影響で飼料用の植物は成長も活発で、栄養価が高い素材を提供できますが、日本では気候的条件から特に冬季では同様の素材を提供できません。
こうした違いは、海外で作成された飼育マニュアルを日本の現場にそのまま適用する際の障壁となることがあります。見た目や名前が同じでも、実際に動物が摂取する栄養成分が大きく異なるため、給餌内容の設計や量の調整にあたっては、各国の食材特性を理解し、現地の実情に即した判断が求められます。
このような点も含め、マニュアルだけに頼らず、現場での観察と柔軟な対応、そして暗黙知の継承が欠かせないのです。
3-2 冬場の飼育管理:風邪をひかせないこと
大型類人猿もヒトに近縁なため、風邪をひいてしまうことがあります。特に冬季は乾燥と低温から呼吸器の免疫力も低下するので丁寧な健康管理が求められます。
しかし私に飼育を教えてくれた師匠からは「風邪をひかせるのは飼育管理が適切でない」と言われていました。
ここでは、その教えを踏まえて特に飼料管理についてお伝えしたいと思います。
飼料に対しての注意点
食性を踏まえた飼料配分
チンパンジー、オランウータン、ゴリラは食性に違いがあります。特に与える樹木や野草等は、その点を踏まえた比率で給餌できることが好ましいです。
同様の体格と仮定して樹木や野草を与える場合に、ゴリラを10とした場合、オランウータン6、チンパンジー2としていました。この比率からも食性の違いが分かると思います。
ゴリラは主に葉や茎などの植物質を多く食べる草食傾向が強く、オランウータンは果実食が中心ですが樹皮なども食べます。チンパンジーは果実食が主体で、時には小型哺乳類を狩って肉も食べる雑食性です。
飼料における繊維質(セルロース)と水分量
健康管理の観点から糖質の少ない野菜を多く与えることは多いと思います。しかし成分としては自生する自然の植物と比べると含まれる繊維質は少なめです。
このような飼料が多いと本来の消化器の働きを再現できません。また含まれる水分量が多いと結果として体を冷やしたり、便を緩くすることにも繋がります。
そのため冬季は消化器活動を促進する繊維質を含み水分量の少ない植物を選択して与えることを留意していました。
例:シイやカシ等の樹木の葉、乾燥牧草
タンパク質を含む飼料は個室で給餌
特に複数で飼育する場合では飼料をバラ撒いて給餌することもあります。その場合は嗜好性の違いや他個体との力関係から片寄った内容の物しか食べれていないことも有り得ます。
そのため摂取して欲しい飼料は個室にて給餌するか当該個体に直接手渡すなどの工夫が必要だと思います。
3-3 心理的・行動的ケアの遅れ
動物福祉は「不快を減らす」から「幸福を増やす」へと進化しています。
エンリッチメント(環境エンリッチメント:動物の生活環境を豊かにする取り組み)やハズバンダリートレーニングなど、動物自身が選択できる環境や、飼育員との良好な関係性に基づいた健康管理が求められます。
ハズバンダリートレーニングとは
ハズバンダリートレーニング(Husbandry Training)は、動物に無理強いせず採血や体重測定などに必要な動作を行ってもらい、健康管理に活かすことが目的のトレーニングです。
2012年頃から動物福祉が重要視されるようになり、全国の動物園が取り組むようになりました。それ以前にも飼育員と動物が良好な関係性を築くための訓練は行われていましたが、一部には人に見せることを目的とした内容も含まれていました。
このトレーニングの最大のポイントは、動物たちが自ら喜んで取り組めること。無理強いしなくとも、動物たちが率先して行動してくれれば、動物の心身にも負担がかからずにすみます。動物に選択肢があり、動物が決して嫌な気持ちを味わわないこと、これこそハズバンダリートレーニングのすばらしさであり、人間と動物との良好な関係性を築けることが重要なポイントです。
しかし実施には人員・設備面の支援が不可欠です。
第4章:大型類人猿の飼育管理とは

4-1 飼育管理上の評価項目
実際に現場で大型類人猿の飼育をしていた時に、私が重視していた評価項目は以下の通りです
- 行動管理
飼育員との関係性の確認、操作する質の向上 - 飼料管理
植物の繊維質の厳選と飼料配分 - 心理的配慮
個体の反応を無視しない、親近感と安心感 - 施設環境
機能的で飼育個体と交流が量りやすいか - 生い立ち
飼育歴、自然哺育か人工哺育か等
普段から担当個体の搬出や新規個体の導入も視野に入れ、飼育員自身が個体の分析と自らの飼育管理の評価を行う事で課題が見えてきます。
4-2 飼育管理に対しての格言
長年の経験の中で大切にしてきた言葉があります
- 観て考えろ
- 猿の言うこと聞いてやれ
- 困らないようにしておけ
これらの格言は、暗黙知を端的に表現したものであり、マニュアルには書かれていない現場の知恵そのものです。
特に重要なのは、大型類人猿たちに安心感を与えることです。
第5章:未来に向けた提言

5-1 経験知の保存と伝承の仕組みづくり
ベテラン飼育員の暗黙知を、映像やインタビューでアーカイブ化し、若手との実地メンタリング制度と連動させることで、知識継承の仕組みを構築できます。
5-2 科学と経験値の融合を意識した現場判断の出来る人材の育成
マニュアルを”使いこなす”視点を育てる教育が必要です。「こうすべきだから」ではなく、「なぜそうすべきか」を考える研修と、現場の創意工夫を尊重する文化が鍵になります。
5-3 組織的な支援体制の確立
飼育員任せでは限界があります。福祉投資として、分野ごとの専任スタッフ・十分な時間・予算・機能的な施設の整備、研修制度など、組織全体でのバックアップが不可欠です。
5-4 飼育の経験知と科学的手法の融合へ

国内にて培われた飼育の経験知と現代の科学的手法の両方を融合させた飼育技術の再構築が国内における大型類人猿の飼育の課題を克服出来る道だと思います。
それは飼育されている大型類人猿の個性を尊重し豊かな暮らしを提供する事にも繋がるはずです。